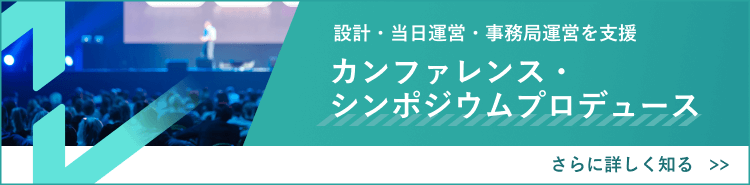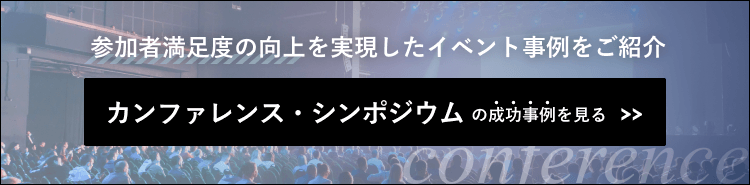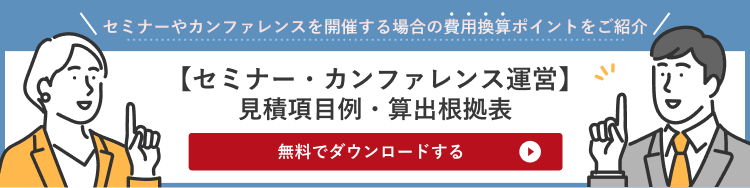社員総会や株主総会の進め方、開催前の準備について解説!
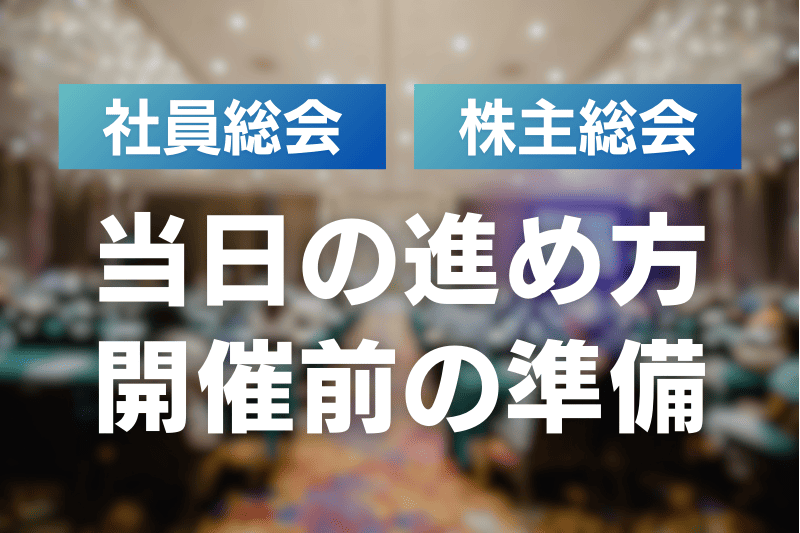
企業や団体では、年度や期の節目に開催される「総会」。実は総会と一口にいっても、株主総会や社員総会(全社総会・キックオフ)といった種類があります。
総会ごとに目的や進行方法が異なるため、いざ担当者になると「何から手をつけるべきか分からない」と戸惑ってしまうかもしれません。
今回は、社員総会や株主総会の概要や特徴、各総会開催に必要な準備や進め方、総会の開催形式の選び方などについて解説していきます。
総会の準備から運営までプロがワンストップでサポート!詳しくはこちら
目次
総会とは?
総会とは、企業や団体において、経営方針や活動内容の報告・共有・意思決定を行うための重要な会議やイベントです。
一般的には「社員総会」と「株主総会」に分けられ、それぞれの目的や出席者、進め方が異なります。
なおニューズベースでは、社員総会・株主総会の両方に対応し、企画から当日運営までトータルでサポートいたします。オンライン・オフライン・ハイブリッド形式など、ご要望に応じた柔軟な対応が可能です。運営支援をご希望の方は、株式会社ニューズベースへぜひお気軽にお問い合わせください。
社員総会
「社員総会」には2つの意味があります。
1つは、一般社団法人やNPO法人などにおける意思決定機関としての「社員総会」です。これは法人の構成員(=社員)が集まって、事業報告や役員選任、定款変更などを審議します。
もう1つは、株式会社で行われる社内イベントとしての「社員総会」です。こちらは、年度や四半期などの節目に開催される全社イベントのことです。「全社総会」「キックオフ」「○○Day」など、企業によって呼び方はさまざまあります。
社内イベントとしての社員総会では、前期の業績報告や社員表彰、次期の経営方針の共有などとともに、企業理念の再確認や社員同士の交流を目的としたコンテンツが組み込まれることが少なくありません。そのため、株式会社における社員総会は、社内の一体感を高める、企業文化を醸成する場として、多くの企業で重視されています。
株主総会
「株主総会」は、株式会社における最高意思決定機関であり、株主が出席して会社の経営方針や重要事項を決議します。主な議題には、取締役・監査役の選任、決算や配当の承認、定款変更、合併などが含まれます。会社法により、年に1回以上の開催が義務付けられている点も特徴です。
【社員総会】当日の進め方
社員総会は、年度や四半期などの節目に合わせて実施されることが多く、企業にとっては情報共有・組織の一体感醸成・企業文化の浸透を図る重要な社内イベントです。
ここでは、社員総会でよく取り入れられる企画や内容、当日の進め方について解説します。
社員総会の主な内容・企画
社員総会のプログラムは、会社の文化や目的に合わせて多様に構成されますが、大きく分けて「情報共有」「称賛・評価」「理念浸透」「交流・エンゲージメント強化」といった要素で構成されることが一般的です。
以下に代表的な企画内容を紹介します。
| 経営方針・ビジョンの共有 | 新年度の経営戦略や全社の方向性を経営陣から直接伝えることで、組織のベクトルを揃える狙いがあります。 |
| 業績の振り返り・各部門の報告 | 前期の成果や課題を振り返り、部署ごとの実績や取り組み事例を共有することで、全社的な理解と学びを促します。 |
| 表彰式・MVP紹介 | 優れた業績を挙げた社員やチームを表彰し、モチベーション向上とロールモデルの可視化につなげます。 |
| 新入社員・新任役員の紹介 | 組織に加わったメンバーを紹介し、歓迎の意を伝えて一体感を高めます。 |
| 企業理念やバリューの再認識 | ミッション・ビジョン・バリューの再確認を促す演出やスピーチを取り入れ、企業文化の浸透を図ります。 |
| パネルディスカッション・クロストーク | 経営陣と現場の社員が対話形式で語り合い、双方向の理解や納得感あるコミュニケーションを実現します。 |
| ワークショップ・グループディスカッション | チームビルディングを目的とした参加型企画です。部門横断で課題に取り組み、部門間の連携強化を目指します。 |
| 懇親会・レクリエーション企画 | オフライン開催の場合は、軽食を交えた懇親会やゲーム・抽選会などのカジュアルな企画により自然な交流を促すこともできます。 |
| 演出や映像によるブランディング効果 | 映像、音楽、照明を活用したオープニング、感動的なまとめ映像などを取り入れるなどして、社員の記憶に残る印象的なイベントをつくることも可能です。 |
当日の進め方の例
ここでは、参加人数50〜300名程度、来賓あり、社員総会・表彰式・懇親会を含む半日〜終日開催を想定したスケジュール例を紹介します。
| プログラム内容 | 補足 | |
| 12:30〜12:40 | 開会・オープニング映像 | 映像や音楽を用いて雰囲気づくりと集中を促す |
| 12:40〜13:10 | 経営方針・事業方針の共有 | トップからビジョンや戦略の発信 |
| 13:10〜13:40 | 各部門からの実績報告 | 成果や課題を全社で共有 |
| 13:40〜14:10 | 表彰式 | MVPや新人賞など、個人・チームの功績を称える |
| 14:10〜14:30 | クロージングスピーチ・理念共有 | 企業の価値観の再確認と未来への激励 |
| 14:30〜15:00 | 休憩・会場転換 | 会場のセッティング変更やリフレッシュ時間 |
| 15:00〜18:00 | 懇親会やレクリエーション | 飲食・歓談・来賓挨拶・レクリエーションなど |
上記はあくまでも一例です。企業規模や開催目的に応じて、企画内容やセッション時間を柔軟に調整しましょう。
【株主総会】当日の進め方
株主総会は、以下の6ステップで進行されていきます。
- 議長を選任
- 出席者の確認〜開会の宣言
- 総会成立の報告
- 議案審議
- 議長の解任
- 閉会宣言
株主総会の主な内容と流れ
株主総会の主な流れと内容は以下の通りです。
① 議長を選任
はじめに議長を選任します。
議長とは、総会を進行する人のことです。議長を選任する方法としては立候補が一般的ですが、誰も立候補しない場合には推薦での選任となります。
② 出席者の確認〜開会の宣言
議長を選任したら、出席者が全員揃っているかを確認します。
出席者の確認完了後、「本日はお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。」と挨拶し、「これから〇〇の〇〇総会を開催いたします。」と総会の開催を宣言します。
③ 総会成立の報告
株主総会の場合、開催するためには議決権を行使できる株主の議決権数の過半数を有する株主が出席することが条件となります。
無事に条件を満たすことができたのであれば、「議決権総数◯戸のところ、本日の通常総会出席議決権数◯戸により議決権総数の半数に達しており、本通常総会は成立いたしました。」と、総会が成立したことを報告しましょう。
④ 議案審議
出席者同士で意見を出し合い、議案を審議していきます。
時間になったら、出された意見に対して最終的に採決を採り、議案を成立するかどうかを決めていきましょう。一般的に出席者の過半数の賛成があれば、議案の成立です。
⑤ 議長の解任
議案審議が終了したら、議長は「これをもって議長の任を解かせていただきます」と宣言して解任となります。
⑥ 閉会宣言
最後に「以上で第〇〇期通常総会を終了させていただきます。」と閉会を宣言すれば、総会が終了となります。
総会の開催に向けた準備内容
総会の開催に向け、以下のことを準備していきます。
- 開催方法の決定
- 開催場所の決定
- プログラムの決定
- 進行台本・マニュアルの作成
- 開催の連絡
- 機材の準備
- リハーサルの実施
それぞれ解説します。
開催方法の決定
社員総会や株主総会は、開催形式によって準備内容や当日の対応が大きく変わります。
以下では、オフライン、オンライン、ハイブリッドそれぞれの開催形式の特徴や準備内容の違いについて紹介します。
オフラインでの開催
オフライン開催とは、参加者が同じ会場に集まり、直接対話できる形式です。臨場感や一体感を醸成しやすく、表彰や交流など「場の空気」が重視されるプログラムに向いています。
オフライン開催では、下記のような準備・配慮が必要になります。
- 会場の確保(収容人数、アクセス、設備など)
- 受付・誘導・タイムスケジュールの導線設計
- 感染症対策(必要に応じて)
- 飲食提供がある場合の提供業者・メニュー設計
- 機材手配(音響・映像・プロジェクターなど)
オンラインでの開催
オンライン開催は、参加者がそれぞれの場所からリモートで参加する形式で、移動の負担がなく、全国・海外を含む分散型組織に適しています。
近年はオフライン開催にて社員総会を行うケースが増えています。また、2019年末のコロナ禍の影響により、政府の審査を経た上で株主総会のオンライン開催が認められています。
本来株主総会は「場所」を規定することが求められており、株主総会のオフライン開催はコロナ禍の特例措置として認められていたものです。しかしIT化が進む昨今の流れを受けて、法相・経産相の確認を得た上であればオンライン開催が認められており、今後はその確認も不要とする方向で検討されています。
オンライン開催では、以下のような準備をします。
- 配信ツールの選定と動作検証
- 登壇者の接続テスト・台本準備
- 視聴者用のマニュアル・案内送付
- チャット機能やアンケート機能の活用による参加感の演出
- トラブル発生時のサポート体制整備
ハイブリッド形式での開催
ハイブリッド開催は、会場に集まる参加者と、オンラインで参加する人の両方に対応する形式です。
オンライン視聴者への配慮をしつつ会場の演出や一体感も両立でき、地方拠点・リモート社員など、さまざまな勤務形態に合わせられるのが特徴です。柔軟性が高いことから、社員総会・株主総会、どちらの総会にも適用できます。
ただし、オフラインとオンライン両方の準備が必要になるため、次のように機材・運営体制の難易度が高くなることに注意しましょう。
- 現地会場の音響・照明と配信用の映像・音声を両立させる機材設計
- 進行台本やスピーカーの動線を、両参加者に配慮して構成
- オンライン参加者の離脱防止策(チャット活用・画面切り替えなど)
こうした準備ができれば、ハイブリッド開催は参加者にとって満足度の高いイベントを実現できる形式です。
開催場所の決定
総会の開催場所は、開催形式(オフライン・オンライン・ハイブリッド)に応じて選定することが重要です。
オフライン開催では、アクセスの良さや収容人数、設備の充実度を重視しましょう。プロジェクターや音響設備、レイアウト変更の柔軟性もポイントです。
オンラインやハイブリッド形式の場合は、配信環境(ネット回線、カメラ設置、遮音性など)に対応できる会場かどうかを確認しましょう。
プログラムの決定
総会を成功させるためには、プログラムをしっかり練って決定することが大切です。
社員総会であれば、「方針の共有」「表彰」「交流」といった目的ごとに時間を割り振り、メリハリのある流れをつくりましょう。株主総会の場合は、法的な進行手順に従いながら、必要な議題を無理のない時間配分で整理します。
また、オンライン・オフライン・ハイブリッドといった開催形式によっても、プログラムの組み方が変わります。
例えば、オンラインでは視聴疲れを避けるためにコンパクトな構成を、オフラインであれば交流や演出の時間も含めて柔軟に設計しましょう。
進行台本・マニュアルの作成
総会を円滑に進めるには、進行台本や運営マニュアルの準備が欠かせません。
台本には、プログラムの時間配分や登壇者、使用資料などをまとめ、誰が見ても流れが分かるようにします。
スタッフ向けには、受付や誘導、トラブル対応などを整理した運営マニュアルを用意しておくと安心です。
オンライン開催では、配信開始や切り替えのタイミング、通信トラブル時の対応も明記しておくとスムーズです。
開催の連絡
社員総会では、社内メールや掲示板、社内SNSなどで告知を行います。開催日時や場所、対象者、持ち物、懇親会の有無などを簡潔に伝えましょう。
株主総会は、会社法に基づき原則として開催日の2週間前までに、書面または電子的な方法で招集通知を送付する必要があります。ただし非公開会社の場合は、定款の定めによりこの期間を短縮することも可能です。
機材の準備
開催形式に応じて、必要な機材を早めに確認しましょう。
オフラインでは、マイク・スクリーン・プロジェクターなどの基本設備を、会場の広さや構造に合わせて準備します。
オンラインやハイブリッド形式では、配信機材や回線、音響映像の連携が重要です。
事前のリハーサルとテストを行い、トラブルの予防策も検討しておくと安心です。
リハーサルの実施
総会を開催する前には、必ずリハーサルを行うようにしましょう。
なぜなら、総会を成功させるためには、準備段階が何よりも重要だからです。リハーサルを行わないまま総会を開催した場合、途中で問題が続々と出てきてしまい、想定していた時間を大幅に過ぎてしまうことも珍しくありません。その結果、自社に対する評価が下がってしまう可能性があります。
万全の状態で総会を開催するためにも、最低でも1回、時間に余裕がある場合には3回程度リハーサルを行うようにしましょう。
まとめ
本記事では、総会を開催するにあたっての実際の進め方や実施する前にやるべきことについて解説しました。
最近ではバーチャル総会を実施している企業も増えてきているので、メリットとデメリットを把握した上で開催することが大切です。総会を開催する場合には、参加者へ招集通知を送ったり会場を選定したりする必要があるので、リソース不足に頭を抱える担当者も少なくありません。
そんなときには、株式会社ニューズベースにお任せください。
株式会社ニューズベースでは、カンファレンスやシンポジウム・セミナーのプロデュースなどを行っています。総会の準備から当日の運営まで実績豊富なスタッフがサポートしますので、安心して開催することができます。総会を開催するにあたって、リソース不足や経験が乏しく開催するのが不安に感じているのであれば、まずはお気軽にご相談ください。
本記事を参考に、総会を開催してみましょう。