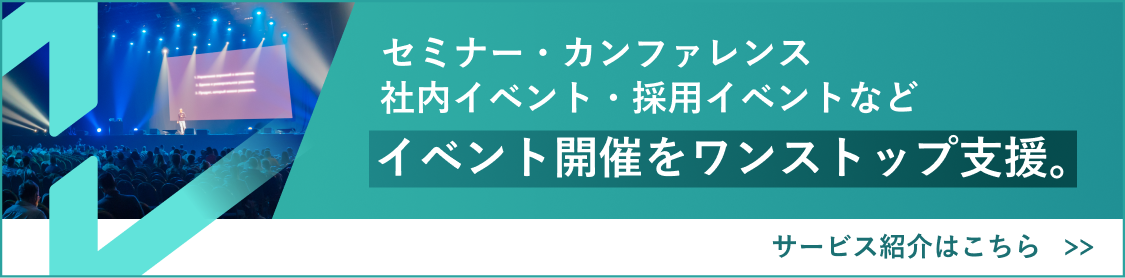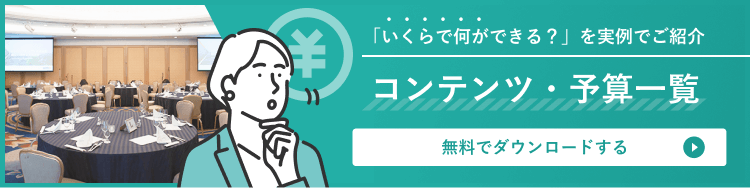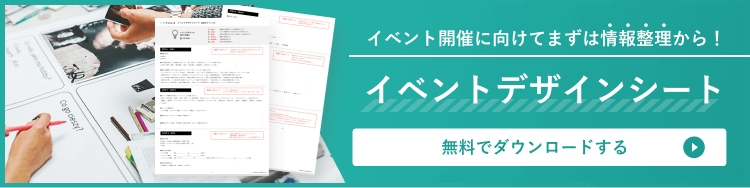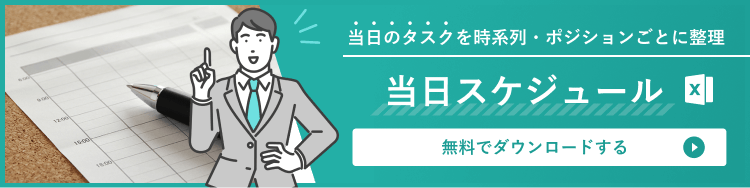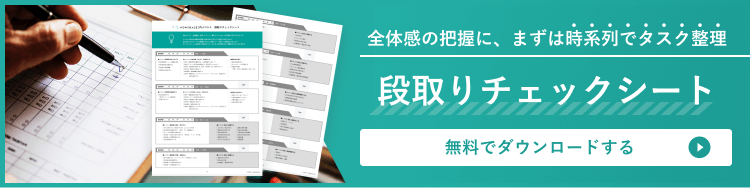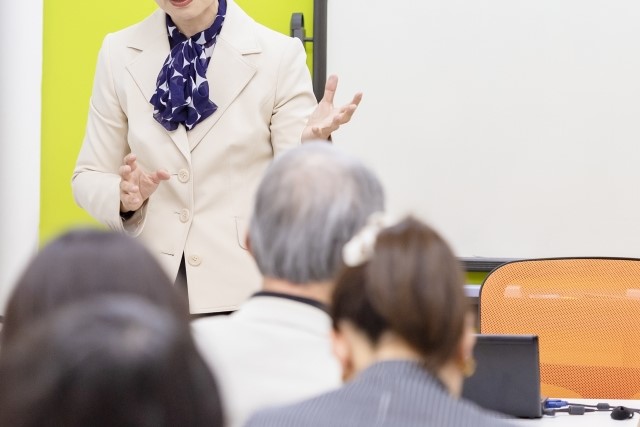表彰式の司会で実際に使える例文とは?成功させるためのポイントについても解説!

社内イベントとして表彰式を開催するにあたって、欠かせないのが司会者の存在です。
予算に余裕があれば司会のプロに依頼するケースもありますが、社員の中から司会者を抜擢する場合もあるでしょう。
司会者は、表彰式をスムーズに進行させるという重要な役割を担っているので、任命された人は「自分にできるだろうか」と不安に感じるかもしれません。
そこで本記事では、表彰式の司会で実際に使える例文や成功させるためのポイントについて解説します。
目次
表彰式は司会者によって大きく左右される
司会者の進行が拙かったり、声が聞き取りづらかったりすると、参加者は式の内容に集中できず、盛り上がりに欠けてしまいます。
逆に明るくはきはきと話しつつスムーズに進行できれば、参加者も安心して見ていられますし、登壇者の緊張も和らぐでしょう。
司会者は、表彰式全体の雰囲気や印象に大きな影響を与える役割であるため、表彰式が成功するかどうかは司会者によって大きく左右されるといっても過言ではありません。
そこで重要となるのが事前の準備です。表彰式全体の流れを把握し、それぞれ適切なタイミングで適切な内容をアナウンスする必要があります。
次章以降で詳しく解説します。
表彰式の一連の流れと司会の例文
表彰式は以下のような流れで開催されます。
- 開会の言葉
- 受賞者の発表
- 表彰状の授与
- 社長の挨拶
- 祝辞
- 受賞者の挨拶
- 閉会の言葉
表彰式の一連の流れと併せて、司会の例文についても紹介します。
1.開会の言葉
まずは開会の言葉で表彰式を開催することを宣言します。
その際に司会者は、軽く自己紹介をしておきましょう。
参加者を表彰式に引き込むために、オープニングに音楽や映像を活用してみるのもおすすめです。
<例文>
お時間となりましたので、これより第◯回 株式会社◯◯の社内表彰式を開催します。
本日司会を務めさせていただきますのは、◯◯課所属の ◯◯(名前)です。
同じく進行役を務めさせていただきます、◯◯課所属の ◯◯(名前)です。(数名で進行する場合)
よろしくお願いいたします。
2.受賞者の発表
次に、社長もしくは代表者が受賞者の発表を行います。
受賞者を発表する際には、「どのような理由で表彰されるのか」についてしっかり説明しましょう。
また、受賞者の名前を間違えないようにするためにも、事前に確認しておくことをおすすめします。
<例文>
これより、〇〇で優秀な成績を収められた社員の皆様への表彰に移ります。表彰状は、
〇〇社長より授与いたします。名前を呼ばれた方はステージへ登壇してください。
皆様、表彰される方々への盛大な拍手をお願いいたします。
3.表彰状の授与
受賞者がステージへ登壇したら、表彰状を授与します。
表彰状の授与が終了したら、拍手を促しましょう。
<例文>
それでは、〇〇社長より表彰状の授与が行われます。〇〇社長、お願いします。
―表彰状の授与終了後―
表彰された皆様、本当におめでとうございます。これからも、さらなるご活躍を期待しております。
皆様、表彰された方々へいま一度盛大な拍手をお願いいたします。
それではステージ上の皆様は、お席にお戻りください。
4.社長の挨拶
表彰状の授与が終わったら、社長の挨拶となります。
受賞者に対するメッセージや今後のビジョンなどについてスピーチが行われます。
なお、社長の挨拶は「表彰状の授与」や「受賞者代表の言葉」などと順番が前後しても問題ありません。
<例文>
続きまして、〇〇社長より挨拶を頂戴します。―挨拶終了後―〇〇社長、ありがとうございました。
5.祝辞
表彰式の開催に伴い、来賓を招待している企業もあります。祝辞をお願いする場合には、一連の流れや持ち時間などについてあらかじめ伝えておきましょう。
<例文>
本日は、第◯回 株式会社◯◯の社内表彰式の開催にあたりまして、多数のご来賓の方々よりご臨席をたまわっております。
はじめに、〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇様よりご祝辞を頂戴いたします。
〇〇様、よろしくお願いいたします。
―祝辞終了後―
〇〇様、ありがとうございました。
続きまして、△△株式会社 代表取締役社長 △△様よりご祝辞を頂戴いたします。
△△様、よろしくお願いいたします。
―祝辞終了後―
△△様、ありがとうございました。
本日、ご出席いただけなかった方々からもお祝いの言葉を頂戴しておりますので、ここで祝電をいくつかご披露させていただきます。(祝電が届いている場合)
―祝電披露―
まだまだたくさんの祝電を頂戴しておりますが、ここからはお名前のみの紹介とさせていただきます。
⬜︎⬜︎株式会社 代表取締役社長 ⬜︎⬜︎様、××株式会社 代表取締役社長 ××様・・・
皆様、ご祝辞ありがとうございました。
6.受賞者の挨拶
受賞者から挨拶をもらいます。
受賞者一人ひとりから挨拶してもらっても問題ありませんが、どうしても時間がかかってしまうので、事前に代表者を決めておくのがおすすめです。
代表者には、一連の流れや挨拶のタイミングについて共有しておきましょう。
<例文>
それでは、本日ここに受賞されました皆様を代表して〇〇さんより、挨拶をお願いいたします。―挨拶終了後―〇〇さん、ありがとうございました。
7.閉会の言葉
最後に閉会の言葉をもらって、表彰式は終了となります。
<例文>
最後に、〇〇副社長より閉式の言葉を頂戴します。
―挨拶終了後―
〇〇副社長、ありがとうございました。
以上をもちまして、第◯回 株式会社◯◯の社内表彰式を閉会とさせていただきます。
表彰式の司会台本を準備する際のポイント
表彰式の司会台本を準備する際に覚えておくべきポイントを紹介します。
台本を作るべき理由
表彰式を行うならば必ず台本を作成すべきです。なぜ台本が必要なのか、以下で解説します。
十分な準備を行うため
台本は準備の漏れをなくすのに役立ちます。
台本を作成すれば、社内表彰式当日の動きの流れが分かります。また、予定にはなかったものの、あるとイベントが盛り上がるような演出も思い浮かぶかもしれません。
さらに、企画時には気づかなかった抜け・漏れを見つけられる可能性があります。
例えば「このタイミングで照明を入れると盛り上がりそう」「印象的な音楽を流したい」「ムービーを流したいので制作しよう」といったことに気づき、準備も捗ることでしょう。
時間管理を適切に行うため
台本を作成すると、時間管理も適切に行えるようになります。表彰式などのイベントは、時間管理がとても大切です。
参加者である社員はもちろん、来賓を呼んでいればその方たちの貴重な時間をもらって開催しています。そのため、時間管理は適切に行われなければいけません。
台本を作成すれば、コンテンツごとにどれくらいの時間がかかりそうか事前に把握できます。また、開催当日も予定時間通りに進んでいるかどうかを容易に確認できることでしょう。
トラブル時もスムーズに対応するため
台本を作っておけば、トラブル発生時にもスムーズに対応できます。
社内表彰式に限らず、イベントでは予期せぬ出来事が発生する可能性があるものです。何らかの問題が発生してしまい進行が中断することもあります。最悪の場合、イベントを止め、中途半端な状態で終幕することもありえます。
そうなれば表彰者の満足度やモチベーションが下がりますし、参加者も戸惑ってしまうことでしょう。台本を作っておけば、機材トラブルなどの問題が起きても、パニックにならずに対応や進行を進められます。
台本の作成準備
台本を作る際には、Wordなどの文書作成ツールを活用します。まずは、台本を作成するために必要な各項目の入力欄を作成していきましょう。
例えば、以下のようなベースを作成します。
| 時間 | LAP | シーン | 画面 | BGM | ナレーション |
それぞれ以下のような意味があります。
- 時間:シーンが始まるタイミングの時間のことです。
- LAP:シーンごとの所要時間のことです。
- シーン:司会挨拶などのコンテンツのことです。
- 画面:シーンごとに入れる参加者に見せるためのスライドや動画の画像です。
- BGM:シーンごとに流すBGMを入れます。
- ナレーション:シーンごとに司会者が読み上げる文章です。
具体的な書き方
では、各項目の具体的な書き方を解説していきます。
シーン
まずは司会挨拶や代表取締役挨拶など、必要なシーンを入れていきます。全体のバランスを考え、一つひとつのシーンが長くなりすぎないように注意しましょう。
ナレーション
シーンごとに適切な文章を入れていきます。セリフの前に名前を書いて、誰が読むべき文章なのか分かるようにします。そして、読みやすいように改行する際には文節で行うことを意識します。登壇者の名前や難しい単語などがあれば、間違えないようにフリガナ表記もしておきましょう。
LAP
ナレーションを実際に読んでみてどれくらいの時間がかかるか測りましょう。それを目安にシーンごとのLAPを記入していきます。
時間
LAPを参考にシーンが始まる目安となる時間を記入します。
画面
流す予定の画面のキャプチャ画像を入れ、雰囲気をつかめるようにします。
BGM
BGMの種類、入れる・止めるタイミング、止め方などを記載して音響担当者に分かりやすいようにします。
事前の練習を必ず行う
台本の記入が全て終わったら、練習として一度読んでみましょう。シーンごとの人の動きなども想像して、足りないものがないか確認することが大切です。また、時間配分が本当に足りているかもチェックしましょう。
また、台本を読むだけでなく、台本を使って練習することも大切です。実際に動きを入れてみると、台本に内容を詰め込みすぎていて時間が足りなくなることが多々あります。
その場合は時間に余裕を持たせたり、不要なコンテンツや文章を削除したりなどしましょう。
トラブル対応について考えておく
万が一のトラブル対応についても考えておきましょう。
台本を作成すると、「このシーンでは人が多くなる」「シーンの切り替えが大変そう」などの課題が見えてきます。
台本や事前練習で分かった情報を頼りに、起こり得るトラブル対応について考えておくと当日も安心できます。
表彰式の司会を成功させるためのポイント
表彰式の司会を成功させるためのポイントは、以下の3つです。
- 盛り上げるタイミングを見逃さない
- 設備や機材の点検をしっかり行う
- 参加者の席次やステージ上の立ち位置を把握
順番に解説します。
盛り上げるタイミングを見逃さない
司会を淡々と行っているだけでは、味気のない表彰式となってしまいます。
受賞者にとっていい思い出にするためにも、司会者は盛り上がるタイミングを見逃さないことが重要です。
具体的には、表彰状が授与されたタイミングで拍手を促したり、声のトーンを上げたりすることを意識してみましょう。
設備や機材のリハーサルをしっかり行う
表彰式では音響設備や照明機材などを用いますが、中でも司会者にとって音響設備は重要です。
マイクの音量が適切か、異音が発生しないかなどあらかじめ細かくチェックしておく必要があります。
会場の備品を使う場合や機材のレンタルを受ける場合は、提供業者によるチェックがありますが、自社で準備する場合は十分にリハーサルを行い、問題がないことを確認しておきましょう。
参加者の席次やステージ上の立ち位置を把握
受賞者や来賓の方の立ち位置や、座る位置などをあらかじめ決めて確認しておきましょう。
ここで時間がかかってしまうと、メインコンテンツである表彰式に行くまでに間延びしてしまうためです。
席次表を作成して運営と出席者で共有する、案内役のスタッフを配置するなどの対策もしておくと良いでしょう。
まとめ
本記事では、表彰式の司会で実際に使える例文や成功させるためのポイントについて解説しました。
司会者によって表彰式が成功するかどうかが決まるといっても過言ではありません。
そのため、表彰式を成功させたいのであれば、盛り上げるタイミングを見逃さないようにしたり台本を準備したりするなどの対策を講じましょう。
実際に使える例文についても記載しておりますので、本記事を参考にしてみてください。
弊社、株式会社ニューズベースでは社内コミュニケーションイベントプロデュースを提供しており、工程管理や会場の準備・当日の進行管理など、表彰式の支援を行っています。
トータルでのサポートはもちろん、ピンポイントでの対応も可能です。
豊富な支援実績もありますので、まずはお気軽にご相談ください。