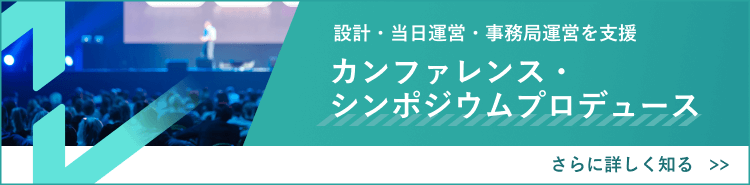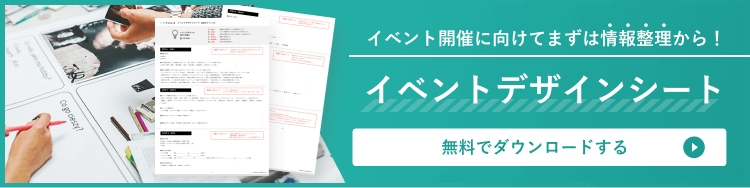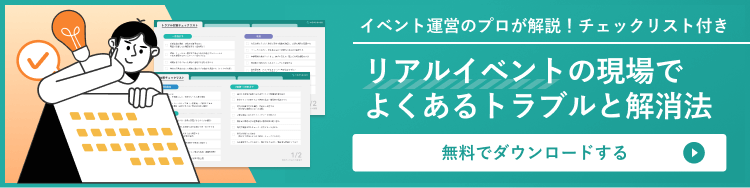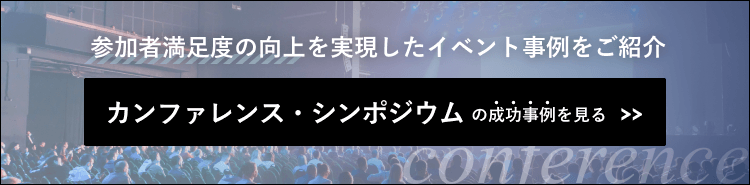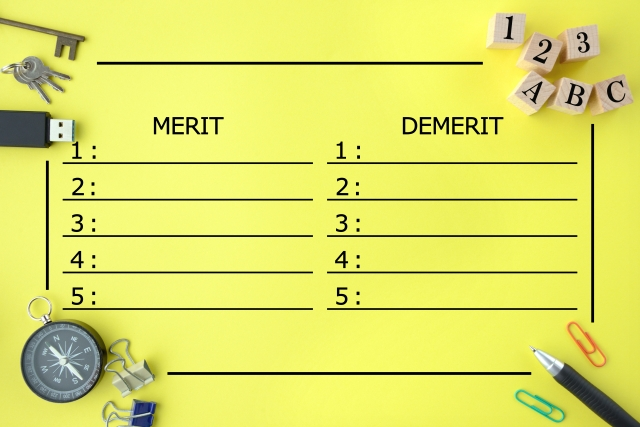シンポジウムの進行表作成のコツとテンプレート紹介

シンポジウムでは多くの関係者が関わるため、当日の進行表が不可欠です。特に、複数の講演者同士でディスカッションを行う際はつい時間オーバーになってしまうこともあるため、司会進行がとても重要になります。
また、投影資料や映像を使用する際も、どのタイミングでそれらを使うのかを予め把握しておく必要があります。会場参加者からの質問を受け付ける場合は、質疑応答の時間の設定や予め質問を受け付けるなどの工夫も必要です。
そこで今回はシンポジウムの進行表作成のコツについてご紹介します。
目次
そもそもシンポジウムとは
シンポジウム(symposium)とは、ある特定のテーマについて、数人の論者が登壇してそれぞれの発表を行うイベントのことです。
「公開討論会」「研究発表会」と日本語で訳されることもあります。発表後、聴衆から質問を求めてそれに論者が答える質疑応答の場が設けられることが一般的です。
シンポジウムや開催準備について詳しくはこちらの記事もご覧ください。
シンポジウム進行表作成のコツ
シンポジウムの進行表を作成するにはいくつかのコツがあります。精度の高い進行表を作るにはどうすればよいのでしょうか。
ポイントを決める
まず進行表作成に取り掛かる前に、当日どのような出来事があるのかポイントを決めましょう。ポイントを決める際は、当日の運営に影響の大きいポイントから決めることが重要です。
例えば会場設営、講演者との事前打ち合わせ、来場者の受付、本番の開始、休憩など大まかな項目を決めておき、次に中項目、小項目へと分解していきましょう。
ポイントを決めて順番に配置し、進行表のアウトラインを作成していきます。アウトラインを作成できた時点で抜け漏れがないかを確認するのがよいでしょう。アウトラインを作成することで、抜け漏れのない進行表を早く正確に作ることができます。
時間配分
アウトラインを作成したら、次にそれぞれの項目ごとに時間配分を決めましょう。
時間配分は余裕を持って決めておくことが重要です。万が一トラブルがあった際や進行が長引いた際に調整ができるようにそれぞれの項目について最大限必要な時間を見積もっておきます。
そして最大限必要な時間をすべて合わせて合計時間が予定時間をオーバーするようであれば、当日の進行に影響がない項目から優先的に時間を削減して調整していきましょう。
会場の導線・配置
会場の導線、配置もとても重要な要素です。進行によっては、終演時や休憩時間など多くの方が同時に移動するタイミングがあります。そうした時に導線が悪いと混雑してしまい、クレームやトラブルのもとになる可能性もあります。
また会場によっては、講演者の控室から会場までの通路が不便な場合もあります。他にもマイクの位置や照明の位置など、シンポジウムの円滑な運営を実現するために予め確認しておくポイントがたくさんあるのです。
こうした会場の導線・配置は進行表のアウトラインを作成できた時点で、可能であれば実際の会場に足を運んでシミュレーションを行うとよいでしょう。
シンポジウム進行表の記載項目
シンポジウム進行表を作成する場合、イベントの目的を明確にしておくことが大切です。目的が明らかであれば、進行表に記載する内容の方向性もはっきりして書きやすくなります。
一般的にシンポジウム進行表に記載する項目は以下の通りです。
- イベントの概要
- タイムテーブル
- スタッフと役割
- 会場の見取り図
- 緊急時の対応について
それぞれ解説します。
イベントの概要
まずはイベントの概要を明らかにしましょう。イベント名、開催日時、参加予定人数、会場といった基本情報を記載します。いつ・どこで・どのような規模で行うのかがひと目で分かりやすくなります。
タイムテーブル
イベント当日の準備から片付けまでの流れが分かるように、シンポジウム進行表に記載していきます。各段階・コンテンツの開始時間・終了時間を明記しておけば、スムーズにイベントを運営できるためです。
シンポジウムの中で休憩時間などがある場合も必ずシンポジウム進行表に記載します。もしその間に運営スタッフ側で機材の準備などがあるならば、指示内容をあわせて明記しておきましょう。
スタッフと役割
シンポジウムの開催には、数多くのスタッフが必要です。イベント・会場規模、参加人数などが多いほど運営スタッフも多くなります。スタッフが何をすべきか迷わないようにするためにも、シンポジウム進行表には全てのスタッフの役割を記載しましょう。
特にイベント規模が大きくスタッフが多い場合は、どのタイミングでどのような役割があるのかがはっきり分かるようにすることが大切です。
会場の見取り図
シンポジウム進行表には会場の見取り図も記載します。会場の動線を可視化するためです。
イベント会場ごとに大きさや形状だけでなく、搬入経路や駐車スペースなどのルールが異なります。当日になって動線でぶつかりあって進行が遅れるといったトラブルを起こさないためにも、見取り図を記載して事前にシミュレーションなどをすることが大切です。
緊急時の対応について
緊急時の対応マニュアルもシンポジウム進行表に記載しましょう。シンポジウムなどのイベントでは、何らかのトラブルが発生することもあります。自然災害や事故、参加者が急病になるなどを想定しておき、緊急時にどのように動くべきかをマニュアル化します。また、緊急連絡先リストもあわせて記載しておき、万が一に備えるようにしましょう。
今すぐ使える!シンポジウムテンプレート(タイムテーブル)
では、実際にどのような進行表を作ればよいのでしょうか。今回は例としてシンポジウムのタイムテーブルテンプレートを用意しました。
【タイムテーブルの例】
進行表
10:00|運営事務局 会場入り
10:00~10:15|運営事務局 朝礼
10:15~11:00 |音響テスト
11:00~12:00 |昼休憩
12:00|講演者会場入り
12:00~13:00|講演者および運営事務局打ち合わせ
プログラム
13:00~13:35
総合司会 XXXXX氏(経歴)
開会挨拶 XXXXX氏(経歴)
13:35~14:00
基調講演 XXXXX氏(経歴)
14:00~15:00
分科会報告 「テーマ」
A分科会 XXXXX氏(経歴)
B分科会 XXXXX氏(経歴)
C分科会 XXXXX氏(経歴)
15:00~15:20
休憩
15:20~17:00
パネルディスカッション
XXXXX氏(経歴)
XXXXX氏(経歴)
17:00~17:20
パネリストによるコメント
XXXXX氏(経歴)
XXXXX氏(経歴)
17:20~17:30
休憩
17:30~18:00
総合討論
18:00~18:10
閉会挨拶 XXXXX氏(経歴)
18:10~18:25
会場移動
18:30~20:30
懇親会
上記のように、一般的なシンポジウムはいくつかのパートに分かれています。
多くの場合、基調講演があり、分科会報告を行った後、パネルディスカッションやパネルトークが行われます。それぞれの項目で事務局としてはどのような対応が必要であるのかを必ず事前に決めておきましょう。
また、タイムテーブルを作る際の注意点として、ストーリーの一貫性があげられます。シンポジウムには必ずテーマがあるはずです。テーマについて様々な観点から理解や議論が深まるような進行を考えていきましょう。
パネルディスカッションとは?シンポジウムとの違い
シンポジウムでは複数の論者が特定のテーマについてそれぞれ発表し、その後に質疑応答をします。
一方、パネルディスカッションとは、それぞれ視点の違う討論者が集まり、あるテーマについて議論を行って、参加者はそれを聴くというイベントです。
つまり、シンポジウムは一人ひとり発表を行うものであり、パネルディスカッションは複数の討論者が自由に発言・議論するものであるという違いがあります。
パネルディスカッション進行表作成のコツ
パネルディスカッションの進行表を作成する際には次のコツを意識するとよいでしょう。
- アジェンダを決める
- パネリストの意見交換
- リハーサル
上記の3点を意識することで、パネルディスカッション進行表を効果的に作成できます。
アジェンダを決める
アジェンダとは、計画やプランという意味がある言葉です。ビジネス用語として使用されることが多く、ミーティング議題として予定している内容のことを言います。
そのため、パネルディスカッションの場合は、「議論する内容」がアジェンダです。アジェンダをあらかじめ決めておくことでパネルディスカッションをスムーズに進められるでしょう。
また、アジェンダごとに議論する時間を設定しておくことで、時間内に効果的なパネルディスカッションが実施できます。進行表を作成する際には、アジェンダを決め、それについて議論する時間を記載しておきましょう。
パネリストの意見交換
アジェンダについてパネリストから意見をもらっておくと、よりスムーズなパネルディスカッションを計画できます。なぜなら、各パネリストで得意、不得意な内容があるからです。
設定したアジェンダがパネリストの得意な内容ではない場合、パネルディスカッションをスムーズに進行できなくなります。アジェンダの内容についてパネリストと意見交換をしたうえで、アジェンダごとに効果的な回答ができるパネリストへ話しを割り振るよう、進行表に記載しておくとよいでしょう。
以上の2点を意識することで、効果的なパネルディスカッションの進行表が作成できます。
リハーサル
パネルディスカッションの進行表は前述した2点を意識することで完成します。
しかし、進行表を一度リハーサルし、内容が適切であるか確認しておかなければ、実際のパネルディスカッションで効果的な進行が行えない場合があります。作成した進行表をもとにリハーサルを行い、時間内に収まらないアジェンダについては改善していくことが重要です。
このように、進行表が完成したら、一度リハーサルをして効果的なパネルディスカッションが行えるか確認しましょう。
モデレーターの役割
モデレーターには以下のような役割があります。
- 手際よく進行する
- パネリストと聴衆をつなぐ
以下で解説します。
手際よく進行する
シンポジウムにおいて、モデレーターは手際よくイベントを進める進行役という役割があります。事前に作成した進行表に従って、時間通りにコンテンツを進められるようにコントロールしなければなりません。
パネリストと聴衆をつなぐ
パネリストと聴衆をつなぐ役割もモデレーターにはあります。モデレーターは中立的な立場として論者と参加者をつなぎ、場の盛り上げや議論の展開などを行います。シンポジウムのテーマを理解した上で、論者も参加者も「参加して良かった」と思える空間になるよう、両者の架け橋になるように心がけましょう。
まとめ
シンポジウムの運営には進行表が欠かせません。進行表を作る際にはいきなり作り始めるのではなく、ポイントを考えてからアウトラインを作成しましょう。アウトラインを作成したら実際の会場に赴いて配置や導線を確認しながらシミュレーションし、最終的に必要な時間配分を調整していきます。
しかし、完璧な進行表を作ったとしても完璧な当日運営ができるわけではありません。当日の運営は受付や参加者の誘導など多くの細かな業務が必要です。
株式会社ニューズベースなら、シンポジウムの運営を依頼することが可能です。当日の運営はニューズベースのような代行業者に依頼するなどで、自社の負担を減らすことをおすすめします。