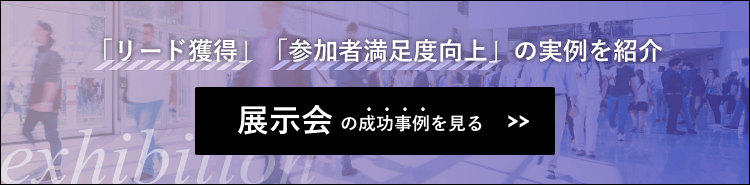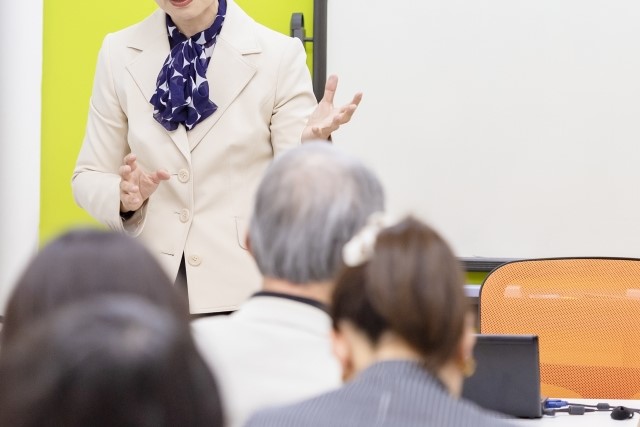展示会を運営する上で発生する業務とは?メリットや成功させるためのポイントも紹介!

展示会を主催者として運営するにあたって、「具体的にどのようなことを行えばいいのだろう?」と頭を抱えている担当者もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、展示会の種類や運営する上で発生する業務、運営によって得られるメリットなどを解説します。
展示会の運営を成功させるためのポイントについても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
展示会は5種類ある
まずは、展示会の種類から把握する必要があります。
展示会の種類は、大きく分けて以下の5種類が挙げられます。
- ビジネスショー
- プライベートショー
- パブリックショー
- 展示即売会
- オンライン展示会
それぞれの特徴を詳しく解説します。
ビジネスショー
ビジネスショーとは、多くの企業が自社の商品やサービスをアピールして新規顧客を獲得したり、認知度を向上させたりするために出展する、BtoBがメインの展示会のことです。
「合同展示会」や「商談会」と呼ばれることもあり、展示会の中では最も王道といえます。
大型会場であれば、数百〜数千以上の企業が出展するため、来場者数が数万人を超えることも珍しくありません。
プライベートショー
プライベートショーとは、一つの企業だけが出展する展示会のことです。
「主催展示会」と呼ばれることもあり、基本的に既存顧客のみが対象となっている招待制であることがほとんどです。
主に既存顧客との関係性を深めることが目的として開催されます。
パブリックショー
パブリックショーとは、一般消費者を対象とするBtoCをメインとした展示会のことです。
代表的な例として、「東京ゲームショウ」や「コミックマーケット」などが挙げられます。
商品やサービスの認知度・売り上げの向上だけでなく、新規ファンの獲得も目的として開催されます。
展示即売会
展示即売会とは、一般消費者を対象とするBtoCの展示会のことです。
その場で商品を購入することが可能となっており、いかに売り上げを伸ばせるかが目的となっています。
通常よりも割引された価格で商品が販売されることが多いため、多くの来場者が見込まれるのが特徴です。
オンライン展示会
オンライン展示会とは、名前の通りオンライン上で開催される展示会のことです。
「バーチャル展示会」や「Web展示会」と呼ばれることもあり、新型コロナウイルス感染症が流行したことで、注目されるようになりました。
オンライン展示会は、会場を準備する必要がないため、コストを大幅に抑えることが可能です。
また、どこにいても気軽に参加できるため、地理的な制約がなく多くの来場者を見込めます。
ただし、オンライン上ということもあり、来場者とのコミュニケーションを図るのが難しかったり、通信環境のトラブルが発生しやすかったりするなどのデメリットがあります。
展示会を運営する上で発生する業務
主催者として展示会を運営する場合、主に以下のような業務が発生します。
- 目的の設定
- 企画の考案
- 会場の選定
- 出展者・来場者の誘致
- 展示会事務局の業務
- 宣伝活動
- 会場の設営
- 本番当日の運営
- 終了後の撤去作業
一つずつ解説します。
目的の設定
まずは「展示会の運営によって最終的にどのようなことを達成したいのか」目的を設定していきます。
ほとんどの場合、商品やサービスの認知度向上や新規顧客の獲得・企業ブランディングの向上などが挙げられます。
設定した目的次第でその後の方向性が大きく変わるため、慎重に決めましょう。
企画の考案
目的を設定したら、「どのような展示会にしていくのか」企画を考案します。
企画は、目的から逆算して考えることが大切です。
実際に開催された展示会を参考にしてみるのもおすすめです。
会場の選定
設定した目標や考案した企画に合わせ、どのような会場が良いかを選定していきます。
展示会を行う会場には、立地・設備・料金などさまざまな要素があります。これら全ての要素が満たされた理想的な会場を探すのは困難です。
そのため、展示会の内容に合わせて、要素ごとに優先順位を決めてから会場を選定しなければなりません。
例えば、自社商品やサービスの認知拡大が目的で多くの来場者を集めたいのであれば、アクセスの良さやキャパシティの大きさを優先します。目的に直接的につながらない要素については、ある程度は妥協しましょう。
また、会場を選ぶ際には下見をすることも大切です。必要な機材・設備はあるか、搬入口の広さはどれくらいかなどを確認します。また、人や物、イベント全体の流れをイメージしながら動線についても確認しておきましょう。
出展者・来場者の誘致
企画を考案したら、出展者・来場者の誘致を行います。
出展者を誘致する際には、必ず展示会の企画やテーマに合っているかどうかを確認しましょう。
出展者のスケジュールを考慮し、余裕を持って半年〜1年前くらいから誘致するのがおすすめです。
展示会事務局の業務
展示会事務局として運営に関わる業務も進めていきましょう。
まず、事務局として運営に関わる準備業務には、以下のようなものがあります。
- 出展企業情報をまとめる
- 特設Webサイトをつくる
- 配布印刷物を制作する
- 当日の受付
- 関係者打ち合わせ
- 警備計画立案
- ステージで行うイベントの段取り打ち合わせ(行う場合)
他にも、展示会を開催する際には以下のような確認・申請も必要となります。
- 会場側と搬入出に関するルール確認や調整
- 飲食展示がある場合は保健所への申請
- 裸火の使用などがあれば消防署への申請
このように、展示会事務局の業務は多岐にわたります。運営スタッフや自社の関係者はもちろん、関係会社などとも連携を取りながら業務を進めていきましょう。
宣伝活動
出展者・来場者の誘致が完了したら、宣伝活動を行います。
宣伝活動の具体例は、以下の通りです。
- DM・メルマガを送る
- 自社のSNSやホームページで告知する
- Web広告を活用する
- プレスリリースを配信する など
展示会の運営を成功させるためには、集客ができるかどうかが鍵となってきます。
そのため、ターゲットとなる顧客に合わせた手法を用いて、十分に宣伝活動を行っていくことが大切です。
会場の設営
宣伝活動を行ったら、会場を設営していきます。
会場の設営は時間がかかるだけでなく、多くの人手も必要となります。
効率よく設営準備をこなしていくためにも、「誰がどの部分の設営準備を行うのか」あらかじめ決めておきましょう。
本番当日の運営
会場の設営が完了したら、いよいよ本番当日です。
本番当日は、展示会を最後まで滞りなく開催するためにも、常にスタッフ同士でコミュニケーションを図りながら、体制を整えることを意識しましょう。
終了後の撤去作業
展示会が終了したら、撤去作業を行います。
撤去作業も設営準備と同様に時間とリソースがかかるため、事前にスタッフごとの役割分担を明確にしておきましょう。
アフターフォロー、反響の調査
展示会終了後は、アフターフォローを行い反響の調査を実施します。
アフターフォローは、展示会へ訪れ自社商品・サービスに興味を持った見込み顧客に対して行います。目的は、将来的な商談化や案件獲得へつなげるためです。
アフターフォローの方法にはメール・電話・DM・SNSなどがあります。これらを組み合わせ、顧客の属性に合わせてバランス良く行いましょう。
反響の調査は、展示会開催の効果を数値で測り、次回の開催や広報戦略に活かすために行います。
来場者数や来場者からのアンケート集計、ブースへ訪れた人の集計、獲得した名刺の集計、商談獲得数の集計などさまざまな角度から調査します。
展示会を運営するメリット
主催者として展示会を運営することで、以下のメリットに期待ができます。
- 新規顧客を獲得できる
- 既存顧客との関係を強化できる
- 自社の宣伝につながる
一つずつ解説します。
新規顧客を獲得できる
展示会は、自社の商品やサービスをアピールするのに最適な場所です。
そのため、来場者に対して自社の商品やサービスの魅力を存分に伝えることで、新規顧客の獲得につながり、売り上げの向上に期待ができるでしょう。
既存顧客との関係を強化できる
展示会には、既存の顧客を招待するケースも多いでしょう。そのため、既存顧客との関係強化の場として活用できるのも、展示会のメリットです。
来場してくれている既存顧客は、既存の商品・サービスについてすでに認知しているだけでなく、自社へプラスの感情を持っています。そのため、新商品・サービスの宣伝をスムーズに行えます。
また、展示会は情報提供や顧客とのコミュニケーションを図れる場です。関係性や顧客の信頼度を高めていけば、長期的に自社商品・サービスを使ってもらうことが期待できます。
そのため展示会では、顧客満足度向上につながるような企画やノベルティの配布、さらにはヒアリングなどを行って良好な関係を築いていくことが大切です。
自社の宣伝につながる
展示会を運営することで、さまざまな形で自社の名前を広めていくことができるため、自社の宣伝につながります。
特に規模の大きな展示会であれば、メディアに取り上げられたり、周囲の施設にポスターを掲示したり、これまで接触できていなかったユーザーの目に触れるる可能性も大きくなります。
認知度を高めることができれば、これまで以上に自社ブランディングを向上できるでしょう。
展示会の運営を成功させるためのポイント
展示会の運営を成功させるためには、企画や集客などの事前準備が大きなカギとなります。
そのため、展示会の目的を念頭に置いて企画立案を行い、目的から絞り込まれたターゲットに向けて効果的に宣伝して集客しなければいけません。
その上で、本記事で紹介してきたように、展示会開催までに行う業務の意味や工程を十分に把握した上で、一つひとつ進めていきましょう。
しかし、展示会を運営するためには、さまざまな業務をこなさなければなりません。
そのため、経験やノウハウがないと「何から始めるべきか」「何をすれば良いのか」が分からないと悩むことになります。
株式会社ニューズベースでは、一つひとつの工程を抜け・漏れなくスムーズに進める道しるべとなる、展示会出展の『工程管理表』を無料で提供しています。
これまで多数の展示会出展をサポートしてきたノウハウが詰まった資料ですので、ぜひご覧ください。
▼ダウンロードはこちら
展示会運営を成功させるために「アウトソーシング」を検討してみませんか?
展示会を開催するにあたって、十分なリソースや時間はもちろん、知識やノウハウも必要となるため、自社だけで運営できるか不安に感じるという方もいるはずです。
展示会の運営を成功させたいのであれば、アウトソーシングを検討してみましょう。
アウトソーシングであれば、展示会の運営における業務の一部を委託できるため、自社の負担を大幅に軽減できます。
また、数多くの展示会を運営してきたプロがサポートするため、効率よく業務を遂行させることが可能です。
株式会社ニューズベースでは、展示会主催者・出展者サポートを提供しており、展示会における事前準備から当日の運営・展示会終了後のアフターサポートまで、トータルで対応しています。
これまで人材業界やウェディング業界・メーカーなど、さまざまなジャンルの展示会をサポートしてきており、年間400案件以上の運営実績があるため、安心して依頼いただけます。
無料見積もりを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
本記事では、展示会の種類や運営する上で発生する業務・運営するメリットなどを解説しました。
展示会を運営することで、新規顧客の獲得や自社の宣伝に期待ができます。
しかし、展示会を運営するにあたって発生する業務が数多くあり、十分なリソースや時間が必要となります。
また、知識やノウハウも必須となるため、自分たちだけで展示会を運営するのが難しいと感じる場合には、アウトソーシングを検討してみましょう。
展示会運営のアウトソーシングなら、株式会社ニューズベースにご相談ください。