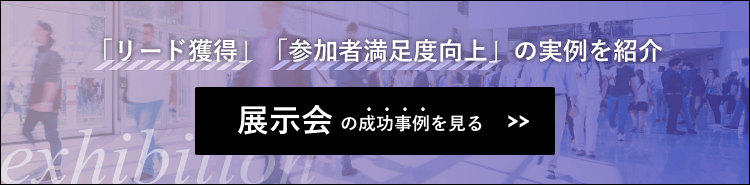【資料DLあり】展示会出展準備のスケジュールを徹底解説!
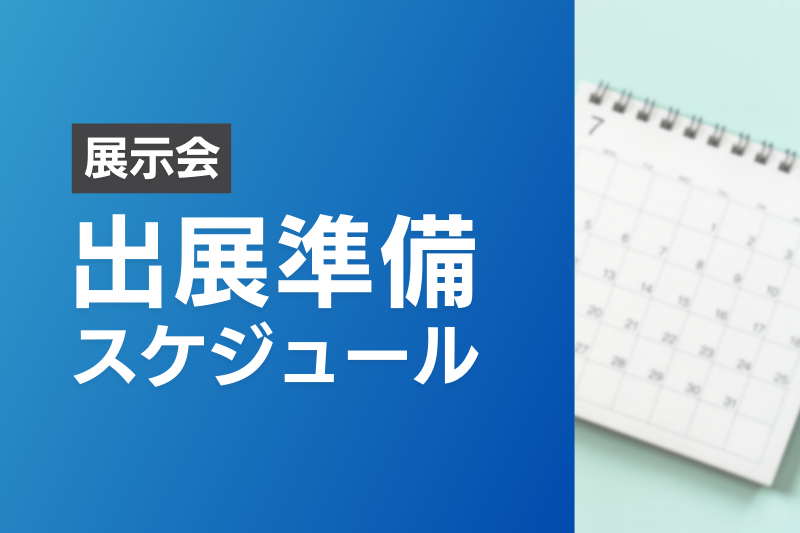
展示会を成功させるためには、準備が何よりも重要です。
しかし、出展経験が少ないと、「どのようなスケジュールで準備していけば良いのか分からない…」と悩んでしまうのではないでしょうか。
展示会の出展準備スケジュールとして一般的な流れは以下の通りです。
- 6ヵ月前:展示会への申し込み、会場下見、ブース決定、企画立案
- 5ヵ月前:目的・目標の決定、スケジュール設定、移動手段・宿泊先の選定
- 3~4ヵ月前:ブース設計・デザイン確定、プロモーション施策の準備
- 2ヵ月前:チラシ・ポスター・パネルなどの制作物発注
- 1ヵ月前:物品搬入、集客・プロモーション開始、ノベルティ・アンケート準備
- 前日:ブース設営、当日の流れの最終確認
本記事では、この流れに沿って、展示会の出展準備スケジュールを詳細に解説していきます。ぜひ参考にしてください。
豊富なノウハウを持つプロのサポートで展示会出展効果を最大化!
目次
【無料】展示会出展スケジュールを簡単に整理できる工程表を配布中!
展示会への出展準備には、数多くのタスクが発生します。スケジュール管理が不十分では、直前になって準備が間に合わなくなることもあり得ます。
そこで、効率的に展示会の準備を進めるために「展示会出展スケジュール工程表」をご用意しました。ぜひご活用ください。
展示会準備スケジュールの全体像
展示会の準備スケジュールは、おおよそ以下のような流れで進めます。
| 準備期間 | 主なタスク |
| 準備開始前 | 出展先の検討 |
| 6ヵ月前 | 展示会への申し込み、会場下見、ブース決定、企画立案など |
| 5ヵ月前 | 目的や目標を決定、具体的なスケジュール設定、移動手段・宿泊先選定 |
| 3~4ヵ月前 | ブース設計・デザイン確定、プロモーション施策の準備 |
| 2ヵ月前 | チラシ・ポスター・パネルなどの制作物の発注 |
| 1ヵ月前 | 会場への物品搬入、集客・プロモーションの開始、ノベルティやアンケートの用意、当日の流れを検討 |
| 前日 | 当日の流れの最終確認、ブース設営 |
この表の流れを頭に入れておき、計画的に準備を進めていきましょう。
【展示会準備のスケジュール】準備開始前:出展先の検討
展示会を成功させるには、まず適切な出展先を選定することが重要です。
自社の製品やサービスをどの市場にアピールするのかを明確にし、出展の目的を決めたうえで、最適な展示会を選びましょう。
- 出展の目的を決める
- 出展先の探し方
- 展示会を選ぶポイント
一つずつ解説します。
出展の目的を決める
まずは展示会の目的を明確化しましょう。展示会への出展は、出展料だけでなくブース装飾や外注スタッフの人件費などさまざまな費用がかかります。
目的がなく、数多くの展示会に出展しても、思うような効果は得られません。費用対効果を高めるためにも、まず展示目的を明確化し、それに合った展示会を選ぶことが大切です。
出展の目的としては、新規顧客の獲得、既存顧客との関係強化、新製品の発表、ブランディングなど、さまざまなものがあります。
どのターゲットに対してどのような訴求をし、その結果何を得たいのか、そうした目的を明確化しましょう。
出展先の探し方
目的が決まったら、それに合った展示会を選定します。出展先候補を探すには、以下のような方法があります。
- 業界団体や商工会議所で情報をチェックする
- 過去の展示会を調査する
- 競合の出展情報を確認する
また、「JETRO(日本貿易振興機構)」では、これから開催されるさまざまな展示会の情報を検索できます。ぜひ活用しましょう。
展示会を選ぶポイント
出展候補をいくつか挙げたら、自社に適した展示会であるかを検討します。検討のポイントは以下の通りです。
- 来場者の属性:狙っているターゲットがいるか
- 開催規模:大規模か、それとも特定業界向けの小規模展示会か
- 出展コスト:予算に合っているか
- 会場の立地:アクセスの良さ、集客力
- 競合の出展状況:同業他社のブース展開など
規模が大きさだけでなく、上記のようなポイントをおさえて吟味することで、目的に合った展示会を選びやすくなります。
【展示会準備のスケジュール】6ヵ月前
展示会準備の6ヵ月前には、以下のことを行います。
- 展示会に申し込む
- 会場の下見やブースの決定
- 企画の立案
展示会に申し込む
目的を決めたら、出展を希望する展示会に申し込みを行います。
展示会によって、会場の規模や場所・出展条件などが異なるため、一つひとつの内容をしっかりと確認する必要があります。
また、各展示会の申込み方法についても確認しておき、申込みが締め切りとなる前に早めに申し込みを行いましょう。
会場の下見やブースの決定
展示会の成功には、会場の下見とブースの選定が欠かせません。
例えば、メイン通路沿いのブースは視認性が高く、多くの来場者の目に留まります。一方で、競合ブースと近すぎると比較されやすく、差別化が難しくなることもあります。
このような点を考慮して、十分に下見をして自社に適したブースを選びましょう。
また、展示内容によっては電源やインターネット環境の確保も重要です。
サービスのデモンストレーションを行う場合、下見をして必要な設備が整っているかを事前に確認しておきましょう。
これらに加えて、ブースの決定方法も確認しておく必要があります。
先着順なのか抽選なのかによって、下見やブース選定をいつ行うべきかが変わるためです。
ブースによっては追加料金がかかるケースもあるため、あらかじめ把握しておきましょう。
企画の立案
出展の目的に沿った企画を立てることで、効果的な展示が可能になります。ターゲット層を明確にし、どのような情報を伝えるかを整理しましょう。
例えば、新製品の紹介やサービスのデモンストレーションを行う場合は、来場者が興味を持ちやすいポイントをおさえた訴求が必要です。
また、集客を強化するために、SNSやWeb広告を活用した事前告知、ノベルティの配布なども検討するとよいでしょう。
展示会の企画立案について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
【展示会準備のスケジュール】5ヵ月前
展示会準備の5ヵ月前に行うべきことは、以下の4つです。
- 目的や目標の決定
- スタッフを選定する
- 具体的なスケジュールを設定する
- 移動手段や宿泊場所を決める
目的や目標の決定
展示会の成功には、明確な目的と目標の設定が欠かせません。
商談の獲得、新規顧客開拓、ブランド認知の向上など、何を達成したいのかを具体的に決めることで、準備や運営がスムーズになります。
例えば、見込み顧客の獲得数や名刺交換数、来場者への認知度向上、商談件数など、測定可能な指標を設定すると効果的です。
ただし、目標数値が高すぎる・低すぎる場合、成果が分かりにくくなります。目的を明確にしたうえで現実的な目標数値を設定し、展示会の成果を最大化しましょう。
スタッフを選定する
展示会に関わるスタッフの選定を進めましょう。
選定するスタッフの人数は、出展する展示会の規模によっても大きく変わるので、事前に確認しておきましょう。
スタッフを選定したら、それぞれの役割についても決めておきます。
具体的なスケジュールを設定する
展示会の準備から当日の運営までの具体的なスケジュールも設定していきます。
展示会当日までの流れを把握し、工程表に落とし込むとスケジュールをより具体的にできます。
まずは、申し込みの締め切りや資料準備などの期限を確認し、6ヵ月前、5ヵ月前と段階的にスケジュールを決定していきましょう。そのうえで、出展申し込み、ブースデザイン、プロモーション施策、配布資料の作成、人員配置といった、各タスクの詳細を設定していきます。
このように、工程表に落とし込みながら具体的にスケジュールを組んでいくと、進捗管理がしやすくなり準備を円滑に進められるようになります。
移動手段や宿泊場所を決める
展示会の会場に向かうまでの移動手段を決めておく必要があります。
車を使って移動する場合には、会場の駐車場を利用するため、申し込み書類を提出しなければいけません。
また、会場が遠い場合には、宿泊場所の確保も忘れずに行います。
開催日が近づくにつれて宿泊できる場所が限られてくるので、なるべく早めに予約しておきましょう。
【展示会準備のスケジュール】3〜4ヵ月前
展示会準備の3〜4ヵ月前に行うべきことは、以下の4つです。
- 必要書類を提出する
- ブースやパネル・ポスターなどのデザインを決める
- ブースの施工会社や物品の制作会社を決める
- 集客方法の決定
必要書類を提出する
展示会の出展に伴い、必要書類を提出します。
必要書類には提出期限が設けられており、不備があった場合には再度提出しなければいけませんので、注意しましょう。
ブースやパネル・ポスターなどのデザインを決める
ブースやパネル・ポスターなどのデザインを決めていきます。
これらは1人でも多くの来場者を自社のブースに集客する重要な役割を担っています。
そのため、これまでの展示会報告書を参考にしながらインパクトのあるデザインを考えましょう。
ブースやパネル・ポスターなどのデザインや作り方について、当ブログではさまざまな記事で解説しています。気になる項目についてぜひチェックしてみてください。
ブースの施工会社や物品の制作会社を決める
ブースの施工や什器・パネル・ノベルティの制作会社を選びます。
ブースの施工会社選びでは、会場の規定に対応できるか、ターゲットにあった装飾ができるかなどが重要です。まずは、過去の実績を確認して候補を挙げていきましょう。
パネル・ポスター制作会社はブランドイメージを適切に反映できるかが重要になります。ノベルティを配布する場合、物品によっては時間がかかることもあるため、早めに業者を選定することが大切です。
展示会の施工会社選びについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
集客方法の決定
展示会で成果を出すには、事前告知から当日の誘導、フォローアップまで計画的な集客施策が必要です。ターゲットに合わせて、以下の3つの段階に分けて具体的な方法を検討・決定していきましょう。
- 展示会前:WebサイトやSNS、メルマガ、招待状の送付
- 当日:ノベルティ配布やデモンストレーション、セミナーなどの実施
- 展示会終了後:顧客・来場者リストから、フォローアップメールの送信や展示会レポートの発信
【展示会準備のスケジュール】2ヵ月前
展示会で使用するチラシやポスター・パネルなどの制作物を外注する場合、2ヵ月前には依頼しておきましょう。
納品された制作物に修正が生じることもあるため、スケジュールに余裕がある場合には、前倒しして依頼することも検討してみましょう。
【展示会準備のスケジュール】1ヵ月前
展示会準備の1ヵ月前に行うべきことは、以下の3つです。
- 会場へ物品などを搬入する
- 集客の開始(メール・DMなど)
- ノベルティやアンケートなどを用意する
会場へ物品などを搬入する
スムーズに設営できるように、会場へ物品などを搬入します。
まず、ブースの設営に必要な物やパンフレット・ノベルティなどの備品をリスト化し、搬入物に漏れがないか確認します。
ちなみに、搬入は自社で行うことがほとんどですが、会場が遠方にある、搬入量が多いといった場合は業者に依頼することも検討しましょう。
搬入時のチェックには、【展示会準備チェックリスト】の活用がおすすめです。無料でダウンロードいただけますので、ぜひチェックしてみてください。
集客の開始(メール・DMなど)
展示会当日は多くの来場者が訪れますが、当日の声掛けだけでは十分に集客できるとは限りません。そのため、1ヵ月前から本格的に集客を開始します。
既存顧客や見込み客にメールやDMで案内するだけでなく、Webサイトでの告知やSNSでの発信によって認知度を高めます。
また、プレスリリースを配信して業界メディアに掲載されれば、新規顧客の獲得にもつながります。
さらに、取引先への個別案内を行い、関係強化の機会とするのも効果的です。
このように事前の告知をしっかり行い、当日の来場者数を確保してチャンスを最大化しましょう。
ノベルティやアンケートなどを用意する
ノベルティやアンケートなどを来場者に渡す場合には、1ヵ月前には用意しておきましょう。
展示会の途中でなくなってしまうと、機会損失につながる恐れがあるため、数は多めに準備しておくのがおすすめです。
【展示会準備のスケジュール】前日まで
展示会準備の前日に行うべきことは、以下の2つです。
- ブースを設営する
- 当日の声掛けやトークスクリプトについて決める
ブースを設営する
仕切りを設置したり装飾を施したりするなど、自分たちのブースを設営します。
ブースのクオリティによって、集客率にも大きく影響する可能性があるため、完成したら問題がないか入念にチェックしましょう。
当日の声掛けやトークスクリプトについて決める
展示会当日は1人でも多くの来場者を集客するために、多くの企業はブースの前で声掛けをします。
スタッフによって声掛けのクオリティに差が出ないよう、トークスクリプトについても事前に決めておきましょう。
自分たちで展示会の出展準備を進められるか不安ならアウトソーシングがおすすめ
今回紹介した展示会の出展準備におけるスケジュールはあくまでも一例です。展示会の規模や企業のリソースによっては、6ヵ月以上前から準備しなければいけないこともあります。
展示会の出展準備は時間だけでなく人的コストもかかります。そのため、自分たちだけで展示会の出展準備ができるか不安に感じる担当者も多いはずです。
そんなときには、アウトソーシングの活用を検討してみましょう。
アウトソーシングを活用することで、出展準備にかかるコストを大幅に削減できます。
また、展示会の出展におけるプロが担当してくれるので、短期間で準備を終わらせることが可能です。
どのアウトソーシング会社に依頼すればいいのかわからないということであれば、弊社株式会社ニューズベースにお任せください。
株式会社ニューズベースでは、展示会主催者・出展者サポートを提供しており、出展準備をトータルで委託できます。展示会当日のスポンサー対応や当日運営の進行管理・来場者の受付などの業務にも対応しています。
これまで数多くの実績があり、展示会に精通したプロが担当しますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
本記事では、出展準備のスケジュールについて詳しく解説しました。記事の内容を参考に、事前に入念な準備を進めておきましょう。
自分たちだけで出展準備を進めるのが難しいのであれば、アウトソーシングの活用も検討してみてください。