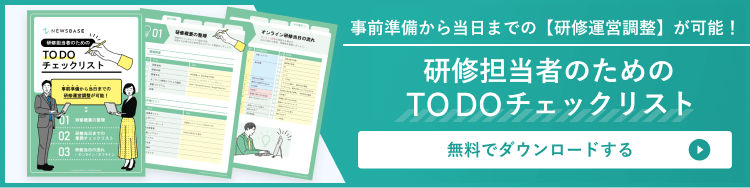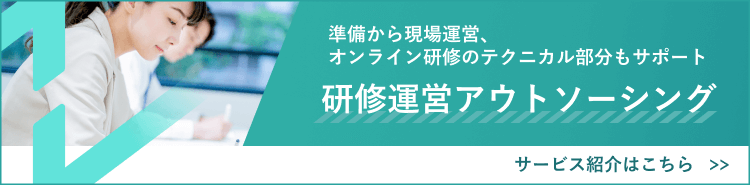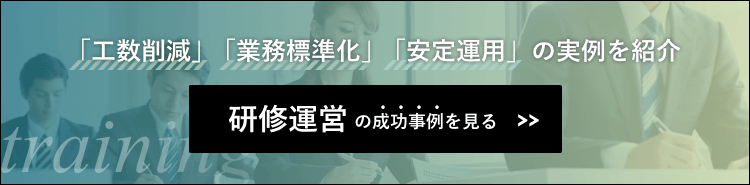研修会の進行表の作り方は?テンプレートや台本の例も紹介
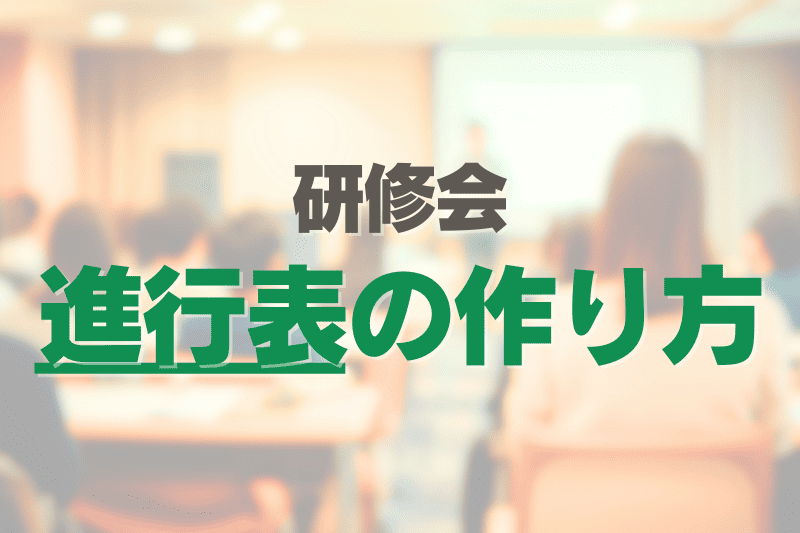
スムーズかつ円滑な研修会やセミナーを実施するためには、進行を滞りなく行うことが重要です。
そのために、前もって当日の動きや内容を把握した進行表やシナリオ、台本などを作成しておくことで、本番では余裕を持って研修会をコントロールすることができます。
本記事では、研修会に役立つ進行表の作り方をはじめ、進行台本のテンプレートや進行及びシナリオを作成する際の注意点について解説します。
なお、株式会社ニューズベースでは、研修会を始めとした各種イベントの企画・運営をサポートしています。
進行表や台本の作成についても、豊富なノウハウと経験を活かして徹底的にサポートいたします。
研修会をより良くしたい場合や、お悩みのことがある場合は、ぜひニューズベースまでご相談ください。
進行表作りに欠かせない事前準備の全体像がわかる資料をダウンロード
研修会運営のアウトソーシングを検討中ですか?
ご質問やお困りごとがありましたら、こちらからご相談ください。
目次
進行表と台本の役割とは?
研修会などのイベントにおける進行表と台本は似ているようですが、それぞれ以下のような違いがあります。
- 進行表:研修会などの構成を時系列に整理して一覧化したもの
- 台本:研修会などの開催において司会進行役が話す内容を中心にイベントの流れを記載したもの
このような違いから、進行表と台本では以下のような役割の違いもあります。
- 進行表の役割:スタッフの役割分担を明確にして関係者へ円滑に情報を共有することで、当日の遅れや混乱を避けるためのもの
- 台本の役割:イベントの進行を円滑にするとともに、研修会をより盛り上げるためのもの
より良いイベントを行うためには、その内容や役割の違いを理解したうえで進行表と台本を作成することが大切です。
研修会の進行表・台本を作成する流れ
研修会の進行表や台本を作成する際の流れやポイントについて解説します。
研修会の目的やテーマを決定する
進行表や台本を作成するうえで最も大切なことは、研修会の目的やゴールを明確にすることです。
参加者にどのような行動を取ってほしいのか、最終的なゴールはどこにあるのかが明確でないと、研修会の内容やスケジュールはブレやすくなります。しかし、ゴールや目的がはっきりしていれば、スタッフ全員がそれを共通認識として持ち、その認識に沿って行動できるようになります。そのためまずは、目的・ゴールを明確にし、それを踏まえてプログラムの内容や時間配分、会場の動線や備品の配置、事前の準備などを進めましょう。
すでに目的やゴールが決まっているのであれば、それを振り返りながら進行表や台本を作成していきます。
研修会のプログラム構成を作る
目的やゴールが明確になったら、研修会のプログラム構成を作成します。
目的・ゴールに合ったターゲット層をイメージしながら、どのようなコンテンツを用意すべきか考えます。講演・ワークショップなどを適切に組み合わせましょう。
長時間連続してしまうと参加者の集中力が切れてしまいますので、適度に休憩などを組み入れる必要があります。
こうしたことを考慮し、開会から閉会までの研修会当日全体の流れをタイムスケジュールでまとめていきましょう。
進行表や台本に落とし込む
研修会のプログラム構成が作成できたら、それを進行表や台本に落とし込みます。
前述の通り、進行表は全体のスケジュール管理や情報共有をするためのもの、台本は司会進行役のセリフを入れて進行をスムーズにしつつ研修会全体を盛り上げるためのものです。それぞれの違いを把握したうえで具体的な内容に落とし込んでいきましょう。
また、研修会当日は必ずしも予定通りに進行できるとは限りません。大小さまざまですが、トラブルやミスが発生することもあります。
進行表にはトラブルに誰がどのように対処すべきか、トラブルを未然に防ぐにはどうすべきかについて記載しておきましょう。
また、余裕をもったスケジュールにすることで、時間の遅れなどが発生しにくくなります。台本には、トラブル発生時の司会進行役の対応やアナウンス内容について記載しておくと安心です。
研修会の進行役が担う役割とは
研修会において、研修の内容とともに重要なのが進行役のあり方です。研修会をスムーズに進めるために、進行役はどのような役割を担うのか見ていきましょう。
・進行表をもとにプログラム全体を進行管理
進行表を基に研修会全体のスケジュールを管理します。セッションやアクティビティを円滑に進めることで、参加者を飽きさせずに時間が超過しすぎないように気を配ります。また、休憩時間の確保も行い、プログラム全体のタイムキーパーとしての役割も果たします。
・参加者への各種案内と誘導
研修会における注意事項や会場の利用方法などを参加者に説明します。各セッションの説明やルールについても伝え、必要な情報や資料の配布なども行います。
・司会進行の調整
全体の進行具合を把握しつつ登壇者とコミュニケーションを取り、司会進行のタイミングを調整します。セッションの切り替え時には進行役がコーディネートすることで進行を円滑にします。
・質疑応答の調整
参加者からの質問・意見を受け付けて整理し、登壇者に渡します。時間配分に注意しつつ、活発な質疑応答となるようにサポートします。
・コミュニケーションを通した満足度アップ
参加者の参加体験を豊かにするために、対話・交流を活性化させます。コミュニケーションを積極的に促進することで、一方的に話を聞くだけではない空間を生み出します。
・問題解決とトラブル対応
研修会の中で、予期せぬ問題やトラブルが発生した際にはスタッフと協力して迅速に対応します。対応後は参加者の不安を解消することで、研修会を改めて進行させます。
進行表作りに欠かせない事前準備の全体像がわかる資料をダウンロード研修会運営のアウトソーシングを検討中ですか?
ご質問やお困りごとがありましたら、こちらからご相談ください。>>お問い合わせはこちら
研修会の進行表テンプレートと作成例
研修会で用いる進行表のテンプレートやその作成例について紹介します。
進行表のテンプレート
研修会進行表のテンプレートは以下の通りです。
・研修会の概要
| 日時 | |
| 場所 | |
| 主催 | |
| 開催目的 | |
| 参加人数 | |
| 全体のディレクション | |
| 運営スタッフ |
・研修会のタイムスケジュール
株式会社◯◯◯◯研修会 進行表 20◯◯年◯月◯日開催
| 開始時刻 | 終了時刻 | 所要時間 | 式次第 | 内容 | 必要なもの | 場所 | 備考 |
| ◯◯:◯◯ | ◯◯:◯◯ | ◯◯分 | |||||
| ◯◯:◯◯ | ◯◯:◯◯ | ◯◯分 |
進行表の作成例
上記の進行表テンプレートを用いて、架空の研修会の進行表を作成しましたので参考にしてみてください。
・イベントの概要
| 日時 | 2025年10月10日 |
| 場所 | 例文ホール |
| 主催 | 株式会社例文 |
| 開催目的 | 自社商品・サービスの認知拡大のため |
| 参加人数 | 50名 |
| 全体のディレクション | 運営責任者:例文 太郎 |
| 運営スタッフ | 企画:田中 一郎(責任者) 山田 次郎 会場係:山田 三郎(責任者) 伊藤 花子 誘導:中村 三郎(責任者) 鈴木 文子 司会進行:高橋 太郎 |
・研修会のタイムスケジュール
例文イベント進行表 2025年10月10日開催
| 開始時刻 | 終了時刻 | 所要時間 | 式次第 | 内容 | 必要なもの | 場所 | 備考 |
| 09:00 | 10:00 | 1時間 | 運営スタッフ会場入り | 会場の設営を行う | ・進行表 | イベント会場 | |
| 10:00 | 10:30 | 30分 | 受付開始 | 参加者の受付と案内 | ・参加者名簿 ・イベント資料 ・アンケート |
会場入口と会場内 | ・受付時に資料とアンケートを配布 |
| 10:30 | 11:00 | 30分 | 開会の挨拶 | イベント概要・流れを説明 | ・司会者用の台本 | ステージ上 | ・ステージ照明 ・音響 |
| 11:00 | 12:00 | 1時間 | 研修1 | ゲスト登壇 | ・マイク ・飲料水 |
ステージ上 | ・ステージ照明 ・音響 |
| 12:00 | 13:00 | 1時間 | 休憩 | 休憩時間の案内とカフェテリアへの誘導 | ステージ上、カフェテリア | ・アナウンス | |
| 13:00 | 14:00 | 1時間 | 研修2 | ゲスト登壇と質疑応答 | ・マイク ・飲料水 ・ボード |
ステージ上、客席 | ・ステージ照明 ・音響 |
| 14:00 | 15:00 | 1時間 | 懇親会 | 立食での懇親会 | 軽食・飲み物 | 客席 | ・音響 |
| 15:00 | 15:30 | 30分 | 閉会の挨拶 | 来場のお礼を述べる・アンケート回収を促す | ステージ上 | ・ステージ照明 ・音響 ・アンケートの回収 ・会場誘導 |
|
| 15:30 | 16:30 | 1時間 | 片付け | 機材の撤収 | ステージ、客席 | ||
| 16:30 | 17:00 | 30分 | 運営スタッフ解散 | 最終17時までに撤収する |
上記の記載内容はあくまでも一例です。研修会内容に合わせて柔軟に記載していきましょう。
進行表に記載すべき内容
研修会の進行表に記載すべき内容は以下の通りです。
・概要:
どのような研修会なのか、その名前や開催日時、会場などの基本情報を記載します。ひと目で何の研修会の進行表なのか分かるようにしましょう。
・当日タイムスケジュール:
当日の会場設営から後片付けまでをタイムスケジュールで一覧化します。例えば、コンテンツを行うタイミングだけでなく、機材準備や会場設営、休憩時間なども記載します。時間配分やコンテンツごとに何をするのかが明らかになっていることで、スムーズに進められます。
・スタッフの役割:
規模が大きくなるほど運営スタッフも増えます。そのため、全スタッフの役割を概要などに記載しておきましょう。コンテンツごとに動くべきスタッフがいるならば、そのタイミングについても記載します。
・会場見取り図:
会場の動線やどこで何をするのかを明らかにするため、会場見取り図を挿入しておきましょう。また、見取り図があることで、緊急時の避難経路についてスタッフ間で共有しやすくなります。
・緊急時の対応:
何らかのトラブルが発生した際の対応マニュアルも記載しておきましょう。誰がどのようなことをするのか、避難経路はどこなのか、時間が押したときはどのコンテンツを巻くのかなどを記載します。
他にも、研修会の運営において必要と思われることは進行表に分かりやすく記載しておきましょう。
トラブル時の進行についてまとめる
研修会などのイベントでは、何らかのトラブルが発生することもあり得るでしょう。
研修会の運営者には、緊急時に備えて避難経路の確保や誘導する義務があります。その義務を全うするためにも、まずは前述のように避難経路について進行表に明記しておくことが大切です。
そして、誰が誘導するのか、誘導方法についても記載しておきましょう。
また、ちょっとした機材トラブルなどでもコンテンツは止まってしまうものです。そのような際にも参加者に混乱を与えないためには、司会進行役を含めてスタッフ全員が適切な対処を行うことが必要です。
進行表の中にトラブル時の対応についても明記しておき、司会の台本には緊急時用のアナウンスのセリフも記載しておくと安心です。
研修会の司会進行における台本テンプレート
研修会をスムーズに実施するには、司会進行役が話す内容を、以下のように台本にあらかじめまとめておくことが大切です。
- 開会(始まり)の挨拶
- 会場案内・注意事項のアナウンス
- 研修会の目的についての説明
- 講師紹介
- 途中休憩のアナウンス
- クロージング
- 閉会(終わり)の挨拶
それぞれ解説します。
開会(始まり)の挨拶
開会の挨拶では、「研修会を受講してもらうことへの感謝」と「自己紹介」の2点を意識した挨拶を行うようにしましょう。
【例文】
みなさま、おはようございます。
本日はお忙しいなか、お集まり頂き誠にありがとうございます。
「〇〇研修会」の司会を務めさせて頂きます「名前」と申します。
これより〇〇研修会を始めさせて頂きます。
→次のプログラムに移行
会場案内・注意事項のアナウンス
研修会場の案内や、各種注意事項に対するアナウンスも重要な項目の一つであるため進行台本には記載しておきましょう。
これらの内容は研修会を実施する上で重要なアナウンスになるため、定期的にアナウンスしたり、重複して話したりすることで、受講者の印象に残るようにしましょう。
【例文】
まもなく〇〇研修会が開会となります。
ここで受講される皆様にお願いがございます。
スマートフォンの電源は皆様のご迷惑になるので、お切りになるか、マナーモードに設定をお願い致します。また会場内には非常口が〇〇箇所ございますので、必ずご確認くださいませ。
また会場内は、飲食及び喫煙は禁止となっております。
(配布資料等あれば)詳細についてはお手元の資料でご確認ください。
研修会の目的についての説明
今回の研修会にはどのような目的があるのかを伝えることも大切です。テーマとともにタイムテーブルを伝えると、参加者が安心して受講できます。
【例文】本日の研修会のテーマは○○です。
各講師が○○について○○分ずつ登壇いたします。○○時からは○○の専門家である○○講師、○○時からは○○の経験豊富な○○講師にお話を頂く予定です。質疑応答のお時間もございますので、みなさまからの積極的なご質問をお待ちしております。
なお、セミナー終了は○時を予定しております。
講師紹介
研修会の講師を紹介する台本も作成しておきましょう。
社外または他の組織から講師に来ていただく場合は、講師の方の略歴を公式プロフィールから抜粋して紹介文を作成します。より魅力的な紹介文をアナウンスすることで、受講者の研修に対する興味関心を高める働きがあります。
【例文】
それでは、これよりご講演頂く「〇〇さん(講師の名前)」のご紹介を簡単ではありますが行わせて頂きます。
講師である〇〇さんは、〇〇大学を卒業後、〇〇株式会社へ入社。
そこで〇〇や△△と言った開発や新規立ち上げに携わられ、現在は〇〇としてご活躍されています。
それでは〇〇さんに御登壇頂きます。
よろしくお願い致します。
途中休憩のアナウンス
長時間の研修会であれば、合間に休憩時間を設けることもあります。
休憩を促す際は、「休憩時間」や「開始時間」など、受講者にとって必要な情報をアナウンスするように心がけましょう。
【例文】
お疲れ様でございます。
本研修会は〇〇構成となっております。
そのため、ただいまより〇〇分間の休憩をとらせて頂きます。
再開時間は〇〇時〇〇分からとなっておりますので、それまでに御着席ください。
クロージング
研修会の終盤では、質疑応答の時間を設けたり、研修会の内容のまとめやアンケートへの回答へのお願いなどを伝えたりします。
【例文】
・質疑応答
登壇者のみなさま、貴重なお話をありがとうございました。ここからは、質疑応答の時間に入らせて頂きます。今回のテーマに関すること、登壇者のお話に関することなどをぜひご質問ください。
・研修会のまとめ
今回は、○○をテーマに研修会を実施させて頂きました。
専門知識豊富で業界実績のある○○さんのお話で、将来の○○における展望が見えてきました。参加者のみなさまからのご意見・ご質問も活発に頂けまして、テーマである○○の重要性がより明確になりました。
お時間ございましたら、今回の研修会のアンケート用紙へご記入をよろしくお願いいたします。
閉会(終わり)の挨拶
研修会の締めとして行う閉会の挨拶では、受講者や講師に対する感謝を伝える文章を盛り込みつつ、アンケートや次回の研修会実施のアナウンス等があれば、そのアクションに結びつける内容を入れるようにしましょう。
【例文】
本日はお忙しい中、〇〇研修会にご参加下さり誠にありがとうございます。
運営を代表して、長時間にわたってご清聴、有意義な意見をお寄せ頂き、心より感謝申し上げます。
これにて〇〇研修会を終了致します。お忘れ物の無いようお気をつけてお帰り下さい。
お時間ございましたら、お手元にありますアンケート用紙にもご回答ください。
またのご来場をお待ち申し上げております。
研修会の司会進行の注意点
最後に、研修会の司会進行やテンプレートを作成する上での注意点について解説します。
一方的に話し続けない
研修会と言うと、つい講師や司会だけが話しがちですが、それでは聞いている受講者は飽きてしまったり、眠くなったりしてしまいがちです。また研修会の時間配分が適正に守られていないと、つい早口になってしまい伝えたいことが伝わらないと言ったケースも見受けられます。
そうならないためにも、一方的に話をするのではなく、課題や疑問を受講者に投げかけてみたり、一人ひとりとアイコンタクトを取ったりすることで、集中力を切らさない工夫をしてみることで研修自体の進行をスムーズに行うことができます。
ボディランゲージや姿勢を意識する
いくらシナリオや台本を作成しても、当日の研修会で受講者をひきつけるような話し方ができなければ、研修自体の満足度や理解度は低下してしまいます。
そのため、台本に記載したセリフだけに意識を向けるのではなく、ボディランゲージや姿勢を意識して話すようにしましょう。そうすることで、受講者の興味を引くこともできますし、全員が聞き取れる声を会場中に出すことも可能です。
研修会は進行表通りに運営するだけでは意味がありません。しっかり受講者にとって満足いく内容を目指すようにしましょう。
規模に応じた会場や内容を設定する
研修会の進行表(テンプレート)やシナリオを作成する際、研修会の規模に応じた会場やプログラムを設定することも大切な項目と言えます。会場までの距離や周辺環境によっては、当日の参加率やアクシデントにも影響を及ぼします。
また、研修会の規模に比例して、会場の設営や機材の設置、受付や誘導などの煩雑さが増していくため、それだけ進行業務も大変になってしまいます。そうならないためにも、事前準備である会場の選定や、プログラムを作成するようにしましょう。
研修会をスムーズにするための4つのポイント
研修会をスムーズにするためのポイントを4点紹介します。
・チェックリストを作成する
・参加者の属性や予備知識の有無について把握する
・研修の代行会社に依頼する
・アンケートを集計してPDCAを繰り返す
順番に解説します。
チェックリストを作成する
研修会では、会場の選定から当日の運営までやらなければいけない業務が豊富にあります。そのため、既に対応した業務と次に自分が対応しなければいけない業務が分からなくなることも珍しくありません。
そんなときにおすすめなのがチェックリストです。チェックリストがあることで、自分が対応した業務と次に自分が対応しなければいけない業務を瞬時に判別することができます。研修会もスムーズに進めることができるので、まずはチェックリストを作成してみましょう。
参加者の属性や予備知識の有無について把握する
研修会にはどのような人が参加するのか、テーマについてどれだけ知っていそうかを事前に把握することは、研修会をスムーズに進めるために重要なポイントです。
参加者の属性や予備知識の有無については、開催前の募集段階である程度把握できます。自社のリストや告知の際にある程度絞り込めるためです。
たとえば、初心者向けの研修であれば、専門用語や業界的な略語は用いるべきではありません。もし専門用語を用いないとスムーズでない場合は、適宜解説を入れるように心がけましょう。
逆に、予備知識が豊富な属性である場合は、専門用語を交えつつ、テーマについてより深く掘り下げられるような進行を意識しましょう。
研修の代行会社に依頼する
研修を開催したいのにも関わらず、人手不足で開催するのが困難な企業も少なくありません。
そんなときには研修の代行会社に依頼するのも一つの手です。研修の代行会社では、講師の手配や業務マニュアルの作成・当日の会場運営などを依頼することができるため、担当者は時間を割きたい業務へ注力することができます。
研修運営のプロがサポートするので、当日の研修もスムーズに進むこと間違いありません。
アンケートを集計してPDCAを繰り返す
研修会が終了した後は、次回の研修会に向けて担当者同士で話し合いをすると思いますが、そのなかでも一番重要なのは参加者の声を聞くことです。
開催者側の視点と参加者側の視点によって考え方や捉え方が大きく異なるため、アンケートを集計して良かった点や悪かった点を聞いてみましょう。アンケート結果を基に研修会を改善するだけで、より充実した研修会が開催できるはずです。
まとめ
本記事では、研修会に役立つ進行表の作り方や進行台本のテンプレート・研修会を進行する際の注意点などについて解説しました。研修会を成功させるためには、いかにスムーズに進行することができるかが重要です。また、チェックリストを作成したり代行会社に依頼したりするのも一つの手です。
代行会社への依頼は弊社、株式会社ニューズベースにお任せください。
株式会社ニューズベースでは、研修運営アウトソーシングを提供しており、年間400案件以上の実績があり、研修の設計段階から当日の運営までトータルでサポートしています。オフラインだけではなく、オンラインでも対応可能なので、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事を参考に、スムーズな研修会を開催してみましょう。
進行表作りに欠かせない事前準備の全体像がわかる資料をダウンロード研修会運営のアウトソーシングを検討中ですか?
ご質問やお困りごとがありましたら、こちらからご相談ください。>>お問い合わせはこちら