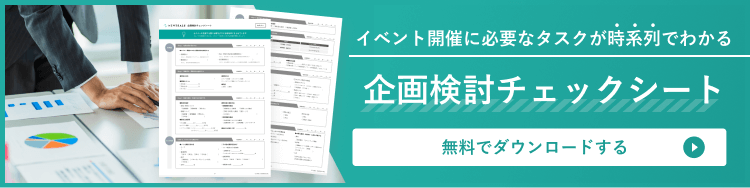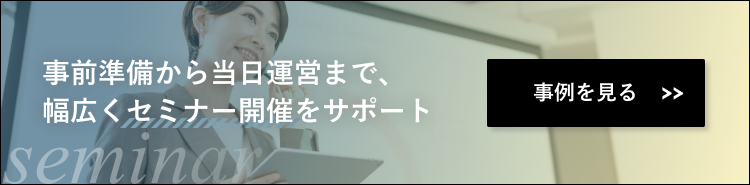わかりやすいセミナーの企画書テンプレート/雛形と書き方をご紹介

セミナーの企画をするにあたって、企画書を作成することはとても重要です。しかし、「効果的な企画書の作り方がわからない」という悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、このようなお悩みをお持ちのご担当者に向けて、企画書の作成において重要なポイントを、実際のテンプレートとともにご紹介していきます。
目次
セミナーの企画書作成で最初に考えるべきこと
企画書を作成する際は「目的」「ペルソナ」「テーマ」を事前に設定しましょう。下準備をしておくことで企画書の軸がブレず、中身の詰まった内容が書きやすくなります。
まずは、企画書作成に必要な下準備を解説します。
目的の設定
目的の設定は、企画書作成の下準備で最も大切です。「新たな見込み顧客を獲得する」「既存の見込み顧客を育成する」「取引を開始した顧客をフォローアップする」など、セミナーの目的を決めましょう。
その際、設定する目的が多すぎると方向性にブレが生じてしまいます。多くても3つまでに絞るとよいでしょう。
また、設定した目標を達成するための手段や、目的を達成すると得られる成果についても挙げておきます。
このとき「販売目標」や「集客数」などの具体的な数値データを用いて作成しましょう。これにより、企画するセミナーが自社の経営目標や課題に見合っているか判断することができます。
目的を設定したら、チームや会社全体に共有し、把握してもらいます。チームや会社から納得されることは、セミナー成功に向けた第一歩です。
ターゲットとペルソナの設定
目的を設定したら、ターゲットとペルソナを設定します。
さらにそこから一歩踏み込み、カスタマージャーニーを作成し、ターゲットについて理解を深めることが大切です。
ターゲットの明確化の重要性
企画書を作成する上で、ターゲットの明確化はとても重要です。
例えば、ターゲットを「会社員」とだけ設定すると、世の中の全ての会社員が対象になります。これではターゲットが絞り込めたとはいえず、具体的な企画も立てにくくなることでしょう。
ターゲットを設定する場合は、「IT企業の営業部で働く一般社員」のように、より明確に設定することが大切です。
このように絞り込めば、具体的な企画を立案でき、集客や商品・サービスの訴求をしやすくなります。
ペルソナによってターゲットの悩みを知る
ペルソナとは、ターゲットから想定できる具体的な人物像のことです。ペルソナを設定することで、抱えている悩みや興味のあるトピックを推測しやすくなります。
ペルソナを設定する場合、まずは「属性」「知識・理解度」「業務の実施状況」「セミナー申し込み前の心境・状況」の4項目を当てはめていきましょう。
例えば、先の「IT企業の営業部で働く一般社員」に以下の要素を加えます。
- 性別
- 年齢
- 職業
- 役職
- 業務内容
- 業務上の課題 など
こうすることで、ターゲットからペルソナを生み出すことができます。ペルソナを設定することで、その人が抱える悩みや興味も想像しやすくなり、商品やサービスの購買に至りやすい典型的な顧客像を把握することができます。
カスタマージャーニーでターゲットを深く理解する
カスタマージャーニーを作成することで、ターゲットについてさらに深い理解を得られます。
カスタマージャーニーとは、ペルソナが商品やサービスの購買に至るまでの行動や心理を知り、各段階の検討フェーズに応じてどのようなアプローチをするのが効果的かをまとめたものです。ターゲットについてより深く理解できるとともに、社内での認識を共有するのに役立ちます。
より質の高いセミナーを開催するためにも、ターゲットとペルソナの明確化、そしてカスタマージャーニーについて考えましょう。
KPIを設定する
KPI(重要業績評価指標)の設定も、セミナーの企画書作成では大切です。
以下に、セミナーにおける一般的なKPIの設定項目を紹介します。
申込者・参加者数
申込者や参加者の数は、どのようなセミナーであってもほぼ必ず設定すべきです。
申込者数のKPIを設定する場合、理想とする成果から逆算して設定します。例えば、最終的な受注数を設定したら、案件数、商談・相談数を設定していき、最後に目標の申込者数を設定します。設定したターゲットや予算を加味して、できる限り現実的に設定しましょう。
商談数
商談数はBtoBの場合に設定することが多いものです。
商談数をKPIに設定する場合、セミナーから実際に生まれた商談数を計測する必要があります。また、商談そのものは営業職に行ってもらうため、営業部との連携が必要です。
満足度
企業と参加者のエンゲージメント(親密度)を高める目的で行うセミナーでは、満足度をKPIの設定項目にします。また、前述の商談数をメインKPIに、満足度をサブKPIにして観測することで、次回以降のセミナーの質向上に活用することも可能です。
通常、セミナー開催前にアンケートを配布して、開催後にアンケート回収を行います。アンケートの回答項目は「満足していない」から「とても満足」までの5段階評価にすると集計しやすく、参加者にも負担がかかりません。
理解度
理解度も満足度と同様に、企業と参加者のエンゲージメント向上やセミナークオリティの向上を目的とするケースでKPI設定します。満足度と同じように、「理解できなかった」「よく理解できた」といった5段階評価の回答形式にすると集計しやすくなります。
セミナーのテーマの設定
最後に、目的やペルソナを設定した上で、セミナーのテーマを設定しましょう。
テーマを決める際に重要となるのが、最初に決めたセミナーの目的です。これが例えば「顧客獲得」なのか「認知拡大」なのかでは、適切なテーマが大きく異なります。
仮にセミナーの目的が「新たな見込み顧客を獲得する」である場合は、テーマを自社商材に設定しても問題ありません。
一方、「自社商材の認知を拡大したい」場合のセミナーで自社商材のみをテーマにしてしまうと、セミナーが失敗してしまう恐れがあります。なぜなら、そのセミナーには自社商材のことを知らない人は参加しないと思われるためです。
具体例として、「勤怠管理サービス」を取り扱う企業によるセミナーにおいて、目的が新規見込み顧客獲得の場合、テーマは「導入を検討している人向けの勤怠管理サービスの選び方・使い方講座」が考えられます。一方、目的が認知拡大の場合は「勤怠管理業務の負担を減らすノウハウ」などといった内容が適しています。
テーマの設定は、目的を満たしつつペルソナの悩みに応える内容にすることが重要です。
企画の作り方がわかる!資料を無料でダウンロード
セミナー企画書に必要な項目や書き方・作り方を解説
企画書には、イベントの目的や実施計画が網羅されている必要があります。
なぜなら、イベントを円滑に進めることが目的で利用されるからです。
企画書はイベントの開催許可を得る目的や、実際に動き始める際の打ち合わせ資料としても使用されます。そのため、企画書にイベントの目的や実施計画が明確に網羅されていなければ、イベントを開催できなくなってしまう可能性もあるので、とても重要です。
企画書を実際に書く際には、先ほども説明した「目的」が明らかになっていなければなりません。これはセミナーを開催する目的を関係者に周知徹底する必要があるためです。そのため、実際の意図からずれた内容になってしまっては、せっかく企画したセミナーも失敗に終わってしまいます。
また、オンラインで開催するセミナーの場合には、従来の企画書とは異なった点があるため、注意が必要です。
そこでここでは、セミナー企画書に必要な項目や書き方・作り方を解説していきます。
企画書に書くべき内容とは?
セミナー企画書には、以下のような情報が盛り込まれている必要があります。
滞りなく準備、運営ができるように、抜け漏れなくわかりやすい企画書を作成しましょう。
→名称は仮とし、あとで正式に決める形でも大丈夫です。
・目的
→セミナーの来場者にどんな価値を与えるのか、どんな行動を期待するのかを定義づけましょう。
・場所
・日時
・参加費用
・参加人数
・セミナー開催までの段取り
・セミナー当日の段取り
・予算
・購入が必要なもの、またどこで購入するのか
・購買担当者
・準備が必要なもの
・準備担当者
セミナーの「目的」をベースに、上記の項目を検討してみてください。
オンラインで開催するセミナーの場合には、上記の項目以外に利用するツールや通信環境などの項目が追加されます。また、オンラインで行うため、場所という項目が不要になる場合もあるため、状況に応じた項目を記載するようにしましょう。
企画書の作り方
企画書の作り方はさまざまな方法がありますが、先ほど解説した項目等を記載するといったことに違いはありません。
企画書の作り方は下記の通りです。
- 紙に記載して作成する
- パワーポイントを利用して作成する
- ワードを利用して作成する
- その他ツールを利用して作成する
紙に記載して作成する方法は、現代では古いといわれる方法ですが、ツールを利用するより文字として書くほうが企画をまとめやすいという方もいます。そのため、文字のほうがまとめやすい方は紙に記載する方法がおすすめです。
パワーポイントやワード、その他ツールを利用して作成する方法は、パソコンを利用して作成する方法で紙に記載する方法より企画を比較的まとめやすいというメリットがあります。そのため、企画書の作成で迷った場合には、パワーポイントやワード、その他ツールを利用することがおすすめです。
企画書の作り方は、紙媒体とデジタル媒体どちらも基本的には下記の順で記載されます。
- タイトル
- 現状・分析
- 目的
- 概要・コンセプト
- 施策・効果・予算・スケジュール
- 目標
上記の内容を1枚でまとめられるとわかりやすく伝わりやすくなります。
企画書と提案書の違い
企画書と提案書は仕事を円滑に進めるために必要なものという点では同じなため、違いがいまいちわかりにくいということが多いです。
しかし、明確な違いがあります。企画書は主に社内で利用されるものであり、提案書は主に顧客に対して利用されます。そのため、企画書を作成する場合には企画をわかりやすく資料にまとめ、社内で共有し、提案書を作成する場合には顧客のニーズに合ったものを資料にまとめ、提示します。
また、企画書と提案書の2種類を利用する際には、基本的に提案書を出してから企画書を出すので注意してください。
企画の作り方がわかる!資料を無料でダウンロード
企画書テンプレートはどこでダウンロードできる?
実際に企画書に盛り込む内容がわかっても、フォーマットに悩む方も多いかもしれません。
企画書を書く際は、Webに公開されている無料テンプレートを利用するのが便利です。Webに公開されている企画書のテンプレートを利用することで、時間をかけずに目的に合わせた企画書が作成でき、コスト削減などにもつながります。
[文書]テンプレートの無料ダウンロード
「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」というサイトのテンプレートには、企画書に必要な以下の項目が設定されているので、欄内に記入するだけで企画書が完成します。
いくつか雛形の例をご紹介します。
- 趣旨・目的
- 日時
- 場所
- 内容
- 講師
- 対象者
- 日程・スケジュール
- 研修[講演会・セミナー]の目的
- 研修[講演会・セミナー]日程・場所
- 対象社員
- 研修[講演会・セミナー]内容
- 必要経費概算
- 研修[講演会・セミナー]日程・場所
- 対象社員
- 研修[講演会・セミナー]内容
- 必要経費概算
- 目的
- 日程・場所
- 対象社員
- 内容
- 必要経費概算
- 現状・課題
- 目的
- 内容
- 実施スケジュール
本テンプレートはWordファイルで作られているので、編集も容易にできます。開催するセミナーに応じて、必要項目の追加・削除のうえ使用してみてください。A4サイズのテンプレートなので、印刷して関係者に配布するのにも便利です。
上記で紹介した企画書のテンプレートを利用することで、時間をかけずに企画書の作成が可能になります。しかし、良い企画書を作成するためには、テンプレートに沿って記載する以外に注意することがあります。
注意することとは、5W2Hと企画書が完成したら第三者に確認してもらうことです。
5W2Hは下記のことです。
- Why(なぜ) なぜイベントを行うのか
- What(何を) 何をやるのか
- Who(誰が) 誰が行うのか
- When(いつ) いつ行うのか
- Where(どこで)どこで行うのか
- How(どのように)どうやって行うのか
- How much(いくら)価格・費用・コスト
この5W2Hを意識し、完成したら第三者にチェックしてもらいましょう。
ビズ研
企画書テンプレートのダウンロードは、ビジネステンプレートが登録不要・無料でダウンロードできる「ビズ研」の利用がおすすめです。
企画書テンプレートには、標準の「企画書」に加えて「イベント企画書」「新商品企画書」など用途に合ったテンプレートが利用できます。
WordやExcelなどのツールを使用すると、項目や列の編集・追加も可能です。自由にカスタマイズできるため、自社用のフォーマットとしての利用にも効果的です。
また、企画書の書き方や見本例・サンプルなども掲載されているため、書き方に困った際は参考にしてみると良いでしょう。
⇒【ビズ研】
500Mails
「500Mails」では、用途に応じた様々な企画書テンプレートが公開されています。
テンプレートの配布だけでなく、効果的に企画書を書くにはどうすればいいのかも解説されており、企画書を作成する際に参考にするといいでしょう。
ExcelファイルやWordファイルで作成されているので、記入や項目の調整を簡単に行うことができます。セミナー企画・運営までに必要な企画書テンプレートが網羅されているのも便利です。
⇒【500Mails】
企画の作り方がわかる!資料を無料でダウンロード
まとめ
本記事では、これからセミナーの企画をしようとしているご担当者に向けて、企画書に盛り込むべき内容や、便利なテンプレートをご紹介しました。
イベント開催は企画書作成以外にも時間が必要なことが多くあるため、どのように進めていくのかが重要になります。その際にイベント開催のプロの力を借りるとより円滑に進められるようになります。
株式会社ニューズベースでは、お客様の目的に沿ったセミナーやイベントを開催するお手伝いをいたします。なるべくロスやリスクなくセミナーを開催したいとお考えでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ニューズベースによるセミナー開催サポート事例も公開中